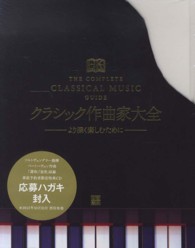内容説明
「どうせ分かってもらえない」をときほぐす。最注目の言語哲学者、一般書デビュー!
目次
第1部 理論編 言葉の本質(人間の言葉は魔術だ;「言語化」の手前にあるもの;あいまいさが生む言葉の本質;空気・皮肉・げんかつぎの言語学)
第2部 応用編1 嘘、誤解、もどかしさ(聞き手をコントロールするコミュニケーション;誤解のメカニズム)
第3部 応用編2 生きるに値する孤独な世界(文化の尊重と、個人の尊重;自分らしさの言語学;「月がきれいですね」が「あなたが好き」になるとき)
著者等紹介
小野純一[オノジュンイチ]
1975年、群馬県生まれ。自治医科大学医学部総合教育部門哲学研究室准教授。専門は哲学・思想史。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。ベルギー・ゲント大学文学部アジア学科研究員、東洋大学国際哲学研究センター客員研究員などを経て現職。本書が初の一般向け著作となる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件