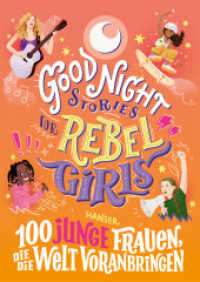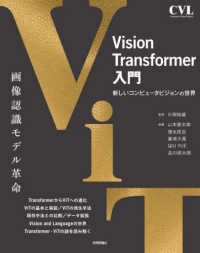内容説明
GAFA v.s.国家、勝つのはどちらか?ニュースではわからない「本質」を、テクノロジー×政治×経済の視点で読み解いた全ビジネスパーソンの新・教養。
目次
第1章 デジタルテクノロジーの現代史
第2章 ハイブリッド戦争とサイバー攻撃
第3章 デジタルテクノロジーと権威主義国家
第4章 国家がプラットフォーマーに嫉妬する日
第5章 デジタル通貨と国家の攻防
最終章 日本はどの未来を選ぶのか
著者等紹介
塩野誠[シオノマコト]
経営共創基盤(IGPI)共同経営者・マネージングディレクター。JBIC IG Partners代表取締役CIO(最高投資責任者)。IGPIテクノロジー取締役。JB Nordic Ventures(Nordic Ninja、フィンランド)取締役。ニューズピックス社外取締役、ビーピット社外取締役。内閣府デジタル市場競争会議ワーキンググループ議員。元・人工知能学会倫理委員会委員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
teddy11015544
7
この分野の歴史、といってもここ何十年の範囲内だが、はとても刺激的で面白いですね。勉強になりました。自分の分野でもあまり拒否的にはならないようにしようと反省。この分野には日本の表意文字と表音文字を使う言語・思考構築とは相性が悪いのだろうか、とも思ったりする。それとソフトウェアなど電子的なものに価値を見出せない国民性。書いてあって厚いもの、ハンコが押してあるものだけに現金を出したがる文化。何の影響でそうなったんだろ?2020/10/24
ゆうすけ
6
終盤にある「これだけテクノロジーが進みコンピューターの計算速度が向上したが世界はより良い場所になっただろうか」という問題意識の中で書かれた本だ。ちょっと類書は思いつかない。第1章だけだとよくあるGAFA論と思わなくはないが、第2章からどんどん本気?になってきます。デジタルテクノロジーが一番親和性が高いのは権威主義国家だという指摘は非常に重い。読み進めるうちに中国で進むすごい勢いでの超国家主義化、それに翻弄される欧州、アメリカ、そして日本と国際政治を観る視点が全然関わってくる。知らない所でこんな戦いが。。2020/11/02
takao
2
ふむ2023/06/13
中嶋 太志
2
現代では、従来の軍事力・経済力・情報・領土に加え、デジタルテクノロジーが国家パワーの規定要素になり、安全保障にも影響する。覇権国にとって、リープフロッグが可能な新興国等に技術を盗まれることは重大な脅威であり、これが貿易摩擦の呼び水となる。安全保障上の脅威は、陸・海・空・宇宙・サイバー空間に存在するが、サイバー空間について完全な国際的コンセンサスはない。データとソーシャルメディアが政治にも大きな影響力を持ち、政府は強大過ぎるデジタルプラットフォーマーに制裁を課す。技術標準の獲得に向け主導権を握る動きが重要。2021/01/24
でんがん
2
デジタルテクノロジーと政治、国家間の覇権についての本。軍事目的でインターネットが生まれたように、DARPAを中心に軍事目的で開発された技術が今後もイノベーションに大きな役割を担うのであろう。一方でSNSの普及により起こった「アラブの春」やFACEBOOKによる非中央集権型の通貨リブラを発行など、いち企業が国家にまで影響を及ぼしうることも言及されていた。日本からはそのような覇権を制する企業は生まれないのか、最終章では日本の今後のあり方も提言されていた。読みやすくて大変面白かったです。2020/12/06