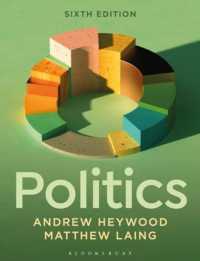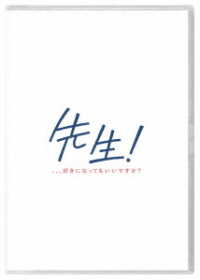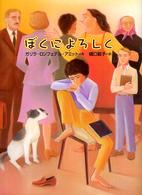内容説明
大学で美術史を学び始めた時からバウハウスは特別な存在だった。その形式や内容ばかりではなく、閉鎖後も様々なジャンルや領域に与えた影響力の強さや人的ネットワークの拡がり、時代やメディアが変換するたびに形を変えながら出現してくるそのヴィジョンの永続性など、100年経ってもバウハウス・マジックは途切れることなく続いている。本書は1980年代から2020年代までの40年近くに渡り、断続的に発表してきた文章に大幅な加筆修正を加えたものだが、そこにはバウハウス100年の旅の過程で起こった思考や視点の変化も刻まれている。(「おわりに」より)。
目次
第1章 バウハウス百年―その創造と教育1919‐2020(100歳になるバウハウス;バウハウス美術館 ほか)
第2章 光の創造体―アクトバウハウス1919‐1999(自然と対峙するバウハウス;ドイツの田園都市構想 ほか)
第3章 ニューバウハウスとダイナミック・イコノグラフィ―空間と視覚の相互浸透(都市のダイナミズム;アメリカの建築ヴィジョン ほか)
第4章 デジタル・バウハウス再考―創造と教育の新たな回路(モダニズムの再考;コミュニケーション環境への移行 ほか)
著者等紹介
伊藤俊治[イトウトシハル]
美術評論家、美術史家。東京藝術大学名誉教授。多摩美大学客員教授。東京大学文学部美術史学科卒業、同大学大学院人文科学研究科美術史専攻修士課程修了。専門の美術史・写真史の枠を越え、アートとサイエンス、テクノロジーが交差する視点から多角的な評論活動のほか、展覧会の企画・キュレーションも行う(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Don2
kaz
キャラ