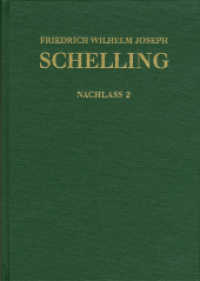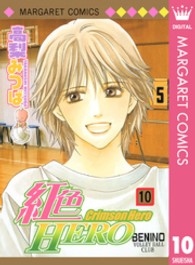内容説明
高校生の声を伝えて、肯定派の目を開きたい。高校生という新たな視点によって、否定派の心を開きたい。すれ違った議論をかみ合わせるために。当事者として古典教育の意義を考えるために。古典教育への興味を広げ私たちの手で、未来へ。
目次
第1部 議論の土台を整える―「高校に古典は本当に必要なのか」を考えるまえに(「高校に古典は本当に必要なのか」のコンセプト;前回のシンポジウム「古典は本当に必要なのか」論点まとめ―近藤泰弘先生、ツベタナ・クリステワ先生の主張も加えて ほか)
第2部 高校に古典は本当に必要なのか(ディベート―高校の授業で古典を学ぶことに意義はあるか;ディスカッション―自由討議 ほか)
第3部 アンケート集計(シンポジウム終了後、現時点で、あなたは「古典を高校で学習する」ことについて肯定派ですか?否定派ですか?;シンポジウムに参加する前と、後で意見は変化しましたか? ほか)
第4部 シンポジウムに至るまで(シンポジウムの出発点;企画の骨組みが決定 ほか)
第5部 共に社会を作る仲間として後進を育てようとするのなら(まとめにあたって;「こてほん2019」をどうとらえていたか ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たろーたん
5
私は否定派。否定派が強かったとかよりも、肯定派が「古典教育が必要」という説得的なロジックを展開できてない。古典教育を目的とするのか手段とするのか。論理的推論や現代語の上達の手段のための古典なら別に古典じゃなくてもいいし、もっと効率の良いものがあるだろう。故に古典教育肯定派は、古典を身につけられることそのものによるメリットを提示しなければならない。ただ、肯定派も、古典そのものが「役に立つ」「面白い」では戦えないことは分かっているから四苦八苦しているのよね。2022/06/30
ひろ
3
2019年に「古典は本当に必要なのか」というシンポジウムが開催されたことを受け、より議論に高校生を巻き込もうとして開催されたのがこれ。高校生が主体となって企画したということにまず驚き、ディベートの中身も前回より質が高かったと思う。自分の中でも、古典について肯定か否定か、まだ意見は固まっていませんが、今現在学ぶことが義務付けられているなら少しでもそこに意義を見出したほうがいいよなあとは思いました。また読み返すと思います。2021/07/31
笛の人
1
これも11月に読んだ本。高校生が主催したシンポジウムの記録です。古典をどうやって継承していくか、真剣に考えなければなりません。その中で、自分は何ができるのか考えていました。わからないけれど、思いついたことからやっていくしかないのかなと思います。自分の役割は橋だと思っているので、沢山勉強して、多くの人に「こんなに面白いんだよ〜」って紹介できるようになりたいです。本書では「原文を学ぶ」という点と合わせてリテラシーが重視されていましたが、私は伝統継承を重視する考えを持っています。2023/11/15
ゆっちゃん
0
高校時代、同じような気持ちでいたことを思い出しました。2024/01/20
りょく
0
結論から言うと、「現行の高校国語科古典教育の在り方は変わらないといけない」ということ。前シンポジウムから①古典は必要なのか、②高校に古典は必要なのか、と来て(少なくとも今回のシンポジウムでは)否定派の論が弱く、結果、高校古典は必要なものとして議論は高校古典の授業内容の改善へと移りつつある。実際、このあと中古文学会や各国語科教育学会等が教育実践の発表や提案を次々と行っており、高校古典教育に関する一連の議論を活発化させる大きなイベントとなった。教育法規や国語科教育史を踏まえた仲島氏の解説は特に必読である。2021/09/24