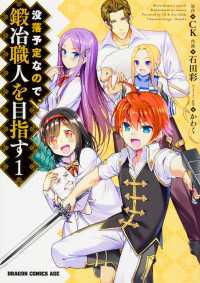内容説明
9・11、相次ぐテロ事件、難民の急増、中東地域の対立…この「暴力」と「分断」はどこから来たのか?目からウロコのイスラム講座!怖がる前に、戦う前に、ちゃんと知ろう。
目次
はじめに 世界を別の角度から見てみると…?
第1回 教えて!タリバンのこと(9・11の報復の名の下、一般人を犠牲にしたアメリカ;なぜ民主主義は根付かなかった? ほか)
第2回 水と油が共生するために(イスラム教徒は異教徒を理由に差別しない;「テロ」という言葉の使用には要注意 ほか)
第3回 タリバンを「悪魔」と見なす前に(豊かなムスリムの国、貧しいムスリムの国;ヨーロッパの「難民」問題 ほか)
おわりに 弱者を守るレジリエンス
著者等紹介
内藤正典[ナイトウマサノリ]
1956年東京都生まれ。東京大学教養学部教養学科科学史・科学哲学分科卒業。同大学院理学系研究科(地理学専門課程)中退。博士(社会学)。専門は多文化共生論、現代イスラム地域研究、地理学。一橋大学教授を経て、同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教授。一橋大学名誉教授。過去にアンカラ大学政治学部、フランス社会科学高等研究院(EHESS)、アバディーン大学で客員教授、ユネスコの人文・社会科学セクターで科学諮問委員を務めた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
崩紫サロメ
26
著者は同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教授で、本書でも扱われているとおり、タリバンと政権側を京都に招き、同志社の学生たちとタリバンのメンバーとが鍋を囲む、という行事を主催した人物である。その点を含め、他の著書との重複点は多いが、アフガニスタンを中心とした入門書であること、そこでイスラム教徒が「西欧社会から見捨てられたと感じること」それが急進化につながっているという指摘は、多くの若い人に読んで欲しいと思う。2022/09/05
Mc6ρ助
14
爺さまはタリバン、アル-カイダとIS(IsramicState)の区別が曖昧であることが露呈してしまった。報道が(情報が)いかに偏って欧米の価値観に基づきなされていることか。また、その欧米的価値観の押しつけに日本が鈍感であることよ。ただ著者の民主主義への理解が浅く多数決を数を制するものが全部取りと疑っていないことを省みるに、日本の未来が暗澹たるものと感じざるを得ない(熟議を尽くすって自民党改憲案では消えているのか?いや、残っていても現政権の人達は無視するだけか?憲法を変える意味はあるのか?あれっ!?)。2022/06/18
CHRONO
10
ちょっとイスラムに寄りすぎた作者が、何とか西洋キリスト圏とも折り合いをつけたいとひねり出したような苦しい解説。特に女性の権利についてずいぶんタリバンを擁護していた印象で、中村哲先生や、長倉洋海さんの本にあった、大きすぎる結納金で人身売買的な一面のある結婚システム。一夫多妻や、若年結婚などの女性の権利侵害については触れられておらず、なんだかなあ。ただ、イスラムとキリスト教世界を融和させたいという気持ちは伝わってきたし、かみ砕いて分かりやすく説明してくれているのはとても良かった。2022/08/03
よきし
9
正直なところまあまあだった。タリバンの背景や欧米によるイスラムフォビアや差別はまったくもって首肯するが、内藤さんの本はいつもイスラムの神学原理主義的なものを肯定し、それを世俗キリスト社会と比較する。逆に世俗イスラム社会の豊かさと現実のイスラム社会の腐敗は問わず、西洋の宗教原理主義の問題も言わない。こうした不均衡な比較でイスラムの正当化を続けているように感じる。その自分の違和感の正体ときちんと向かい合いたいと思う。2022/07/02
かんたあびれ
9
とてもわかりやすく興味深かった。タリバン、アフガニスタン、そしてイスラム諸国。ここ20年何度もニュースで見聞きしたが、理解していない自分を感じていた。知識がほぼない私でもわかりやすく、西側諸国とイスラム諸国の対立の根本である宗教からくる思想や文化の違いや、対立を深くした偏った報道やダブルスタンダードについて理解することができた。こんなにわかりやすく書いて下さり感謝。次は中村哲医師の本を読んでみたい。2022/06/27