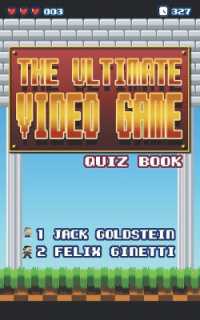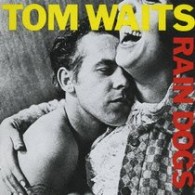内容説明
全財産を失い、右肺の3分の1も失った著者がたどり着いた、新たな贈与論。
目次
1 生きるための負債―人間関係の基本モデル
2 返済するという感覚―ビジネスの起源と交換のモラル
3 見え隠れする贈与―消費社会のなかのコミュニズム
4 「有縁」社会と「無縁」社会―異なる共同体原理
5 明るいその日暮らし―喜捨の原理と交換の「場」
6 21世紀の楕円幻想論―生きるための経済
著者等紹介
平川克美[ヒラカワカツミ]
1950年、東京都生まれ。隣町珈琲店主。声と語りのダウンロードサイト「ラジオデイズ」代表。立教大学客員教授。文筆家。早稲田大学理工学部機械工学科卒業後、翻訳を主業務とする。アーバン・トランスレーションを設立(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
踊る猫
34
高橋源一郎や橋本治、あるいは内田樹に代表される「リベラル」な知識人の姿をこの本の中にも見出してしまった。資本主義や新自由主義から一歩降りて世の中を見渡して、俯瞰する形で経済を問い直す。とはいえスケールは良くも悪くもささやかで、カネに執着せずに生きていられている著者の余裕と諦観が読んでいて、適度にぬるい。読者としての私はこのぬるさに自足したいとも思わないのでもう少し理詰めで社会を捉えたいのだけれど、こうした論者が存在することは論壇の良心であるとも思う。不勉強にして花田清輝を読んでいないので読みたくさせられた2019/08/08
けんとまん1007
34
円ではなく楕円であることの意味。そこに含まれるもの、重なるもの。生き方にも、哲学を持ちたい。2019/06/07
sayan
28
表紙に描かれたコンセプト図に「おっ!」と、思わず手に取った。冒頭からイヌイットの寓話を放り込み、贈与と交換の対立概念につなげる構成が抜群に面白い。「この国では、われわれは人間である」と言い、助け合いに対して礼を言われる筋合いはないと言い切る。さらに「贈与は奴隷を作り、鞭は犬を作る」とまとめる。一方で、ゴールドマンサックスの内部にも共産主義=コミュニティはある、とする切込みは新鮮である。生存するためには、全体給付と多様性といった単語を用いて花田清輝の「楕円幻想(2つの焦点を持つ)」の有効性を著者は支持する。2018/09/30
Kikuyo
27
どちらかを選択しなければいけないという発想で現代人は硬直化している。 真円は中心がひとつ。楕円は焦点が2つ。対立した事象は同じひとつのあらわれで、反発しあいながら他方を必要としている。 現代人はあまりにもきれいに割りきれるものを好むということか。それゆえ考え方は硬直化し、どちらかを「選択しなければならない」思考に陥っている、結果として不具合が生じているということか。 暖かい生身の人間、腐っていく存在としての経済学。貨幣交換は遅延された等価交換。そして貨幣は劣化することのない腐らない商品。2018/09/17
デビっちん
26
著者個人の体験と経済の話、文化人類学の話等、話があっちこっちに飛んでいるように感じました。サラッと1回読んだだけですと、著者が何が言いたくて何に気づいて欲しいかすぐには出てきませんでした。それでも数回回転して得たのは、周囲の関係を断ち切ったある1点で考えるのではなく、それぞれの点が持つ範囲の重なりや集合図で考えるのが良いということでした。そう考えることが、豊かな人間になるかことにつながるんだと思います。2018/08/21
-
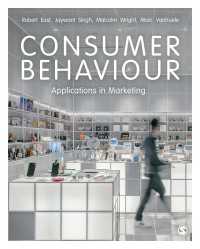
- 洋書電子書籍
- 消費者行動:マーケティングへの応用(第…