内容説明
グリーフケア×死生学。“死別に限らず、人生は多くの喪失体験に満ちている”
目次
序 対話する死生学―喪失とともに生きるために
1章 喪失とともに生きる人たちとの出会い―グリーフカウンセリングの現場から
2章 こどものいのちを看取ること―小児救急の現場から
3章 生を享けること、失うこと―周産期医療の現場から
4章 老病死に向き合う人から学ぶ―終末期ケアの現場から
5章 ホームを失って生きる―路上生活者の語りから
6章 がんが教えてくれたこと―患者・看護師としての体験から
7章 自他の喪失を支えるつながり―グリーフから希望を
終章 死とともに生きることを学ぶ―対話する死生学のために
著者等紹介
竹之内裕文[タケノウチヒロブミ]
1967年生まれ。静岡大学農学部・創造科学技術大学院教授。東北大学大学院文学研究科博士課程修了、博士(文学)。専門は哲学、倫理学、死生学
浅原聡子[アサハラサトコ]
1968年生まれ。GCC認定グリーフカウンセラー、看護師、静岡大学非常勤講師。小児専門病院に20年間看護師として勤務した後、現在はカウンセリング、講演、セミナー等にて活動中。グリーフカウンセリングivy代表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
京都と医療と人権の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
たかこ
59
医療従事者、癌患者、幼い子を亡くした親、自死遺族、ホームレスの方…、多方面からの喪失。今まで他人の死を主に考えていたけれどもし自分が癌だったら…と自分の死についても考えるキッカケとなった。「死者の列」、生まれた時から誰もが死者の列に並んでいる。こんなにグリーフについて勉強したり活動したりしているにも関わらず、自分だけは別というような感覚でいた。確実に私も列に並んでいるのに…。限られた「いのちの時間」の中で、自分に与えられた仕事や役割を果たす、それで他の誰かのいのちが輝き、お互いの存在を照らし合う。2023/08/15
踊る猫
5
「死」という「喪失」を否定するのではなく、それとどう「ともに生きる」か。本書は八つのエピソードが中心となって構成されているが、重要なのはそんな風にして、闇雲に「悲嘆(グリーフ)」を「乗り越える」のではなく悲しみの中に浸り切ることに依って、そしてそれを他者に漏らすことに依って回復して行くか、ということなのだろう。専門的な知識は要らない。門外漢の私でもスラスラと読むことが出来た。特に乳がんを体験し、自分の「死」を是認出来た人の話が興味深い。私は煩悩が多いせいかそこまで悟れそうにはないのだが。今後の参考にしたい2016/06/12
ハル
4
「もう会えない」という事に、驚き、心が震える。日々の中で大切な人を失くしたことは忘れることなく、乗り越えることなく、常にココにある。突然、浮かび上がる幻影に心をギュッとつかまれ涙する日もある。看護という仕事の中に、失くした人の姿を垣間見る。年老うことのなかった大切な人の姿やしてあげられなかったことを、看護師という仕事を通してケアし、ケアされていることを強く感じている。いろいろなことを考えさせられた。いい本だった。繰り返し読むに値する本だ。2016/11/04
ばかぼん
1
・ヨーロッパの臨床心理学の理論⇄日本人の悲しみのかたち ・キュブラ-の五段階説:悲嘆プロセスを辿ることをグリーフワークとし,グリーフケアの一つの方法として感情の表出を促し段階の終局に達するように支援⇄日本人の場合,怒りを人にぶつけない。超越的な存在に取引を望むことも少ない ・喪失者に寄り添う第一歩は慮ることではないか。日本思想や民俗学における悲哀の研究の知見に学び、日本人の悲しみのかたちを知る ・公認されない悲嘆:①同性愛者など,②流産,③子供,④エイズや自死 → 自分の感じている痛みを共有できない2023/02/11
Mihoko
1
色々な立場からグリーフを理解することができる。 そして、自分にたちはだかる問題のよいヒントにもなる書籍。2019/04/20
-
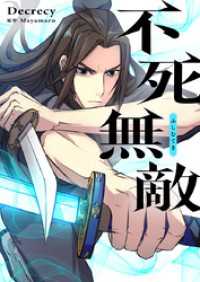
- 電子書籍
- 不死無敵【タテヨミ】第50話 picc…
-

- 和書
- 葵上 能の友シリーズ







