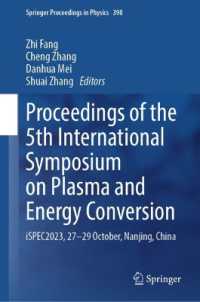目次
1章 これまでの農福連携、これからの農福連携(近年盛り上がりを見せる「農福連携」の取り組み;「農福連携」とはどういう取り組みか ほか)
2章 農福連携・先進事例編(社会福祉法人白鳩会―過疎だって売りにする。六次化農業のパイオニア;京丸園株式会社―障害者雇用でユニバーサル農業へ ほか)
3章 コトノネ的実感的農福連携(福祉から見た農福連携;町に福祉を取りもどす ほか)
4章 農福連携・自然栽培パーティ編―事例(株式会社パーソナルアシスタント青空―ロック魂の自然農;NPO法人縁活おもや―売り方は野菜が知っている ほか)
5章 農福連携座談会・たのしくなければ、農業じゃない
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
R
42
農業と福祉を組み合わせた全国の取り組みを紹介した本。興味深いところが多く、障害者だけではなくひきこもりや、わけありの人たちもまとめて面倒をみている、あるいは、そういう人たちで経済的に自立したコミュニティや企業を作っているというお話。経済と結びつくと成果に直結してしまうが、そこに目標をおかず、自立できるようにゆとりをもって取り組んでいるのがよいようだ。元サッカー日本代表の高原氏が沖縄で農業とサッカーを組み合わせた活動に携わっているというのは知らなかった。慈善的な話ではない段階に進んでいるのがよいと思った。2021/09/04
Kan
5
障害者と農業を結びつけ地域で支える。 障害者だけではなく引きこもりや社会で働くのがしんどい人などの居場所として農業がある。 搾取ではなく、自然のままに(朝日がさして目が覚めて、暗くなれば寝るような)農業をする。それは有機農業や自然農業にもつながる。 2020/09/14
tfj
1
自然の中で仲間と協力しながらマイペースに仕事が出来る農業は、障害者のケアとしても大きな成果を上げていて、福祉分野からも注目されている。一方の農業分野では、耕作放棄地の増加や農業従事者の高齢化が課題になっている。この課題を福祉分野で補完すれば農福共にwin-winになるだろうという、非常に面白い発想だ。 農福連携はSDGsで掲げている未来の姿とも深く一致していて、資本主義社会に疑問を感じ始めている次世代の若者達にも刺さっていくだろう。事例紹介が丁寧かつ情報量が濃密で読み応えがある素晴らしい本だった。2021/01/09