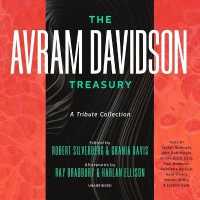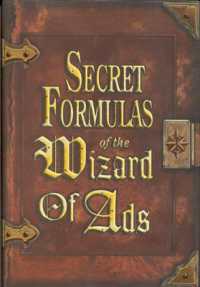内容説明
精神のパラドクス、あるいは間違った判断をする我々。その妄想的な判断の避けがたさと、それに及ぼす言葉の不思議な効果。仏文学の牙城『NRF』誌を長く仕切った編集長、黒幕ジャン・ポーランの洞察。
目次
1 全体性の幻想あるいは精神のもつ数々のパラドクス(プサメニトゥス王の悲しみ;ブリアンを描いた肖像画 ほか)
2 過去の予見あるいは自然なものの探究(暦売り;昨日私は間違えていた ほか)
3 埋め合わせおよび心的遠近法(繊細さについて;一般人と観客 ほか)
4 論法の用い方あるいは理性の宮殿(パラッツォ・デッラ・ラジョーネ)(二つに一つ;いかにして自分の幻想を守るか ほか)
著者等紹介
ポーラン,ジャン[ポーラン,ジャン] [Paulhan,Jean]
1884年12月2日、南フランスのニームに生まれる。ソルボンヌ大学卒業後、マダガスカルで高校教師を務める。1920年よりガリマール社の文芸誌N.R.F.で働き始め、1925年より死去するまで大戦期を除き約40年にわたって編集長を務める。1955年、『O嬢の物語』に序文を寄せる。1968年10月9日死去
安原伸一朗[ヤスハラシンイチロウ]
1972年生まれ。学習院大学文学部卒業。東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻修士課程、パリ第八大学第三課程修了(文学博士)。現在、日本大学商学部准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
R
3
思い込みや、みなしといった当たり前に存在するものについて考える哲学の本でした。プラトンより続く、安心安定の対談形式で、その内容を深く思索していくというのは読んでいて楽しく、少ない分量なのに物凄く重く読み終えた感触がありました。一部を見て全体だと錯覚すること、言葉を入れ替えるだけで事実が誤認されること、かみ合わせることなく議論のように装うことなど、どれもこれもよくあると感じる事象ばかりで考えさせられました。2014/10/28
保山ひャン
0
全体性の幻想あるいは精神のもつ数々のパラドックス、過去の予見あるいは自然なものの探究、埋め合わせおよび心的遠近法、論法の用い方あるいは理性の宮殿、と章立てしてある。「全体性の幻想」というと、難しそうだが、断片的な観察でそれを全体だと考えてしまう傾向のこと。多くの三面記事やエピソードなどから、「ついつい、こう考えてしまうけど、よく考えてみると、それってどうなの?」というような、逆説的な一般大衆あるある、としても読めて面白かった。たとえば、「何もすることがない人の方が、多忙な人よりも遅れてくる」とか。2015/03/27