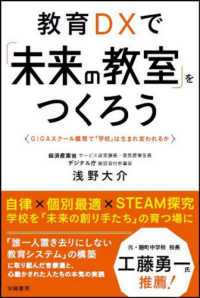内容説明
全国で孤立死の事件が相次いでいる。それは生活保護受給者ですら、例外ではない。悲惨な「死」を防ぐため、わたしたちに何ができるのか?一〇年にわたり、生活困窮者の支援を第一線から実践しつづけてきた著者が、自ら見届けてきた数々の「死」、そして「自立」の具体例をもとに、新しい生活保護、社会福祉のあり方を提言する。
目次
1 すぐそばにあった貧困
2 「不正」か、孤立死か
3 死ぬときくらい、人間らしく
4 ほんとうの自立を支えるために
5 生活保護改革をこう考える
6 新時代の社会福祉をつくろう
著者等紹介
藤田孝典[フジタタカノリ]
1982年生まれ。社会福祉士、NPO法人ほっとプラス代表理事。2002年から東京・新宿区などで、ホームレス支援ボランティアに参加。2004年にはNPO団体ほっとポットを立ち上げ、さいたま市でホームレスの訪問活動を独自に展開し、アパート探しや生活保護の申請支援などをおこなう。反貧困運動においても、反貧困ネットワーク埼玉代表として活躍。2011年には、活動を広げるために新たにNPO法人ほっとプラスを設立。2012~13年に厚生労働省社会保障審議会「生活支援戦略と生活保護制度の見直しを検討する特別部会」にて委員を務めた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
sabato
7
たけしのTVタックルにも最近出演されてましたね(2/24放送)。あの錚々たる出演者の中で、ソーシャルワーカーとして非常に冷静に現場の状況と、社会状況の危機を話されていたと思います(編集はかなりされていたと思いますが)。本書でも書かれていましたが、「生活保護を受けるような貧困には、いつかわたしたちも陥るかもしれない、彼らが自分たちでもあったかもしれない、という想像力です」(p179)。この想像力というセンスこそが、これから最も必要とされる生きる力だと思う。格差や排除からはこのセンスは養われない。2014/02/27
ERNESTO
7
生 保バッシングに対抗して、先ず数字をあげておく。 12年3月現在、受給者数210万8096人、世帯数152万8381世帯。 生活保護問題全国調査会による10年利用率・捕捉率(利用者数)は、日本1,6%・15,3~18%、独9,7%・64,6%(199万8957人)、仏5,7%・91,6%(793万5000人)、英9,27%・47~90%(574万4640人)。 OECD社会支出データベース07年でも、生活保護費の対GDP比は、0.6%、独3,3%、仏4,1%、英5%、米でさえ1,2%で、平均は2%。 2013/06/11
どら猫さとっち
6
内心、極端な話「生活保護なんかいらないんじゃないか」と思っている人たちに、本書を読んで欲しい。世の中には、生活保護なくしては生きていけない人たちが多くいる。その存在を無視して、生活保護引き下げだの、バッシングだのと騒ぎ立てることがおかしい。本書は生活保護の必要性をわかりやすく、熱を持った言葉で語っている。無縁社会が広まって久しい現在、本書は何より重要な存在となり、人間らしい生き方を社会を世に提唱する貴重な一冊になるはずだ。2013/06/22
みったん
6
社会福祉士ってなんだろうって、本当に思う。藤田さんのように、アウトリーチ、ソーシャルアクションといった能動的なソーシャルワークができる社会福祉士ってどれぐらいいるんだろう。人権と社会正義が基盤なのに、なんだかシステムに飲まれてしまっているような。福祉施設就職のための「資格」じゃ意味ないよね。立ち上がれ社会福祉士!尻を叩くような1冊だ。こんな熱い仕事がしたい。2013/03/10
カイ
5
藤田さんは今も現場で活動されている方です。現実を知っているからこそ、その説得力はとても大きいと思う。医療の現場とはまた少し違う形で「人の死」と向き合ってきたんだと思う。「人を殺すな」おそらく言いたいのはこの一言だけなのだろう。個人的には『生活保護を抜け出す一番の理由は死亡』ってことと『貧困問題に対してもバリアフリーの設備と整える』ことにとても共感した。僕達は健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有していることを忘れたくない。2013/04/26