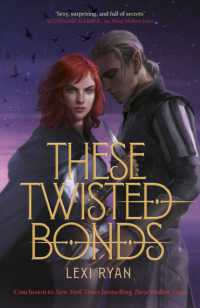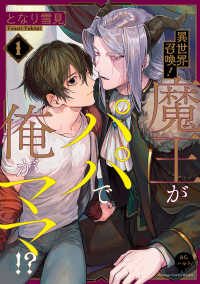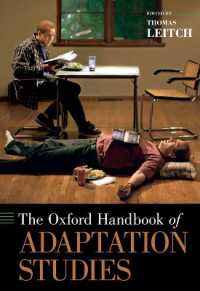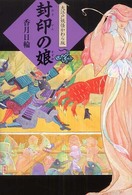出版社内容情報
熱伝導材料におけるフィラーの表面改質,粒径制御,高充填化と粒度分布の最適化
柔軟性,密着性,絶縁性,難燃性,リワーク性,ハンドリング性の実現!
「こんなノウハウが知りたい」が知りたいという方々は必見です!
1.粒子径が異なるフィラーの配合による高充填化へのアプローチ!
2.充填が比較的容易な形状のフィラーの選定と物性のバラツキの改善 !
3.熱伝導性フィラーの樹脂中での分散不良を防ぎたい!分散状態を観察・評価する!
4.フィラーを高充填した際、樹脂の成形性・流動性を確保するには?
5.柔軟な材料を用いて基板の凹凸をへの密着性を上げる!
6.放熱材料の形態に応じた熱伝導率を正確に測定・評価するには?
◎ユーザーからの要求性能・使用される環境
CPU,パワートランジスタ,ヒートシンク,半導体封止財,PDP,電源,バッテリー・・・
◎そのために要求される形状,物性は何なのか?
<形状>
シート,ゲル,グリース,PCM,接着剤
<物性>
柔軟性,密着性,難燃性,絶縁性,流動性,リワーク性,経時安定性,加工性
◎実現するための技術的課題とその対策
・高充填化と流動性の確保
・種類・粒径の異なるフィラーでの充填技術
・分散安定化
・薄化しても割れないシートの加工技術
・正確な熱伝導率の測定と評価法
・高熱伝導をもたらすフィラーの形状とその改質技術
・フィラーの金型磨耗
第1章 電子部品・電子機器における熱問題と対策
熱伝導性材料の
役割
<本章の趣旨>
エレクトロニクス機器では実装部品の発熱密度が急激に増大している。こ
れらの熱対策には放熱面積の拡大と熱伝導率の増大が有効な手段であ
り、接触熱抵抗の低減や材料の熱伝導率の向上がキーとなっている。適
切な材料を選定し、基本原理に適った設計を行うことが重要である。
第1節電子機器における熱設計と対策
1.熱が電子機器に与える影響
2.電子機器の放熱経路と熱対策
3.電子機器・電子部品の放熱能力
4.低熱抵抗化のためのアプローチ
5.放熱面積拡大と接触熱抵抗
6.放熱材料(TIM)の活用
第2節 デスクトップPCの高性能化に伴う諸問題解決への取組み
1. デスクトップPCの熱設計
2. CPUの熱設計電力 (Thermal Design Power)
3. レイアウト設計の最適化
4. CPU冷却方法
5. 熱シミュレーション
6. 環境配慮設計
第3節 ノートPCにおける熱問題とその対策
1.ノートPCの基本レイアウト
2.ノートPCの発熱源
2.1.CPUの発熱量
2.2.CPU以外の熱源
3.ノートPCに使用している冷却デバイス
3.1.冷却ファン
3.2.ヒートシンク/ヒートパイプ
3.3.熱伝導性材料(放熱シート、放熱グリース)
4.ノートPCの放熱量
5.シミュレーション(CFD)を活用した熱設計と実例
6.ノートPCでの騒音低減方法 7.ノートPCの今後の課題
第4節 PDPでの熱問題とその対策
1.ファンの問題 1) 騒音 2) 信頼性
2.PDPの放熱量
3.PDPパネルの放熱
4.回路部の放熱
5.今後の課題
1)さらなる薄型化 2)LSIの高速化、高密度化、1チップ化
3)PDPへの他機器内蔵化(デジタルチューナー、HDD、DVD等)
第2章 高熱伝導性材料のメカニズム
- 混練・分散が熱伝導性特性に及ぼす要因と評価 -
1. 粒子分散複合材料の有効熱伝導率に与える影響と予測式
2 有効熱伝導率に与える影響
2. 1 粒子径や粒子の形状
2. 2 充填量
2. 3 粒子の分散状態
2. 4 分散粒子の配向
2. 5 分散粒子と連続媒体との界面抵抗
2. 6 熱伝導率の異なる多種類の充填材を複合化したプラスチックの熱
伝導率
第3章 各種熱伝導性フィラーの特性と効果的使用方法
第1節 熱伝導性フィラーの種類と特性
1.粒子の製法や評価法の概要
2.粒子モルフォロジー特性のブレイクスルーをめざす先駆的な試み
3.粒子とプラスチックスの分散系に関する製法や評価法の概要
第2節 窒化ホウ素(BN)、窒化ケイ素(Si3N4)、窒化アルミニウム
(AlN)
1.窒化物系フィラーの熱伝導率について
2.窒化ホウ素(BN
) 2.1.BNの特徴
2.2.BNフィラー 2.2.1.BNフィラーの適用例 2.2.2.BNフィラーの問題点及
び対策
3.窒化ケイ素(Si3N4)
3.1.Si3N4の特徴
3.2.Si3N4フィラー
3.2.1.Si3N4フィラーの適用例 3.2.2.Si3N4フィラーの問題点及び対策
4.窒化アルミニウム(AlN) 4.1.AlNの特徴 4.2.AlNフィラー 4.2.1.AlNフィ
ラーの適用例 4.2.2.AlNフィラーの問題点及び対策
第3節 アルミナ(Al2O3)
1.アルミナの特性
2.アルミナの製造方法
3.フィラー用アルミナの特性
4.放熱特性の向上
5.フィラー充填率の向上
3-4.熱伝導性金属粉充填材による高熱伝導化
3-4-2.銀(Ag)、銅(Cu)、その他
第4節 熱伝導性金属粉充填剤(銀・銅・その他)による高熱伝導
化
1. 金属粉
2. 金属フレーク
3. 金属ファイバー
4. 金属の熱伝導率
4. 1銀系フィラー
4.2銅系フィラー
4,3その他
5,複合化技術
第5節 結晶性シリカと球状(アモルファス)シリカ(SiO2)、酸化
亜鉛(ZnO)
1.結晶性シリカと球状(アモルファス)シリカ(SiO2)の概要
2.半導体封止材料用シリカフィラーの概要
3.粒子モルフォロジー特性のブレイクスルーをめざす先駆的な試み
4.酸化亜鉛(ZnO)の熱伝導性フィラーに関する概要
5.各種熱伝導性フィラーの特性と効果的使用方法
第6節 フィラーとしての酸化マグネシウム
1.酸化マグネシウムの特徴
1.1 酸化マグネシウムの製造方法 1.2 酸化マグネシウムの物性
2.熱伝導性フィラーの必要性 3.無機材料フィラー
4.酸化マグネシウムフィラー
5.特許情報からみた酸化マグネシウムフィラーの改質方法
6.酸化マグネシウムフィラーの開発状況
6.1 酸化マグネシウム粉末の耐水性改善
6.2 酸化マグネシウム粉末の粒度分布
7.酸化マグネシウム複合高分子材料
7.1 酸化マグネシウム複合高分子材料の物性
7.2 酸化マグネシウム複合高分子材料の耐水性
7.3 酸化マグネシウム複合高分子材料の熱伝導率
8.今後の開発の方向
第7節 カーボンナノチューブ
1.21世紀の新素材
2.カーボンナノチューブ複合材料の熱伝導性
3.カーボンナノチューブの熱伝導度測定
4.カーボンナノチューブの分散評価
第4章 放熱材料の設計と実例
第1節 熱伝導性シート・フィルムの特性要求とその課題
1.熱伝導性シートの使用方法と分類
2.組成
3.要求特性と課題
3.1 熱伝導性
3.1.1 熱抵抗
3.2 信頼性
3.2.1 特性変化
3.2.2 分解
4.デンカ放熱シートとデンカ放熱スペーサー
4.1 放熱シート
4.2 放熱スペーサー
第2節 シリコーンゴムシート
1.放熱シリコーンゴムシートの特徴と組成
1.1 放熱シリコーンゴムシートに求められる特性
1.2 放熱シリコーンゴムの市場
1.3 放熱シリコーンゴムシートの組成
1.4 ポリマー(シリコーンゴム)について
1.5 熱伝導性充填材について
1.5.1 充填量と熱伝導率について
1.5.2 粒子径、粒子形状と熱伝導率について
2.放熱シリコーンゴムシートの高付加価値化
第3節 非シリコーン系アクリルゴムシート
1.熱伝導性材料の市場と種類
2.非シリコーン系アクリルゴムシート「エフコTMシート」
第4節 エポキシフィルム・シート
1.高熱伝導絶縁接着フィルム
1.1 応力緩和と熱伝導性の検討
1.2 接着性の検討
2.高熱伝導絶縁接着フィルムの用途展開
第5節 PGSグラファイトシートの熱対策への応用
1.PGSグラファイトシートの基本特性
2.PGSグラファイトシートによる放熱、熱分布の均熱化
3.PGSグラファイトシートの応用
3.1ノートPCの放熱
3.2DVDドライブピックアップ用レーザの放熱への応用
3.3半導体製造装置における放熱、均熱
4.今後の展開
第6節 ゲル状フェライトシート
1.ノイズ対策と熱対策
2.ゲル状フェライトシートの特徴
3.ゲル状フェライトシートの性能と評価
4.CPUにおける対策事例
5.ゲル状フェライトシートの今後
第7節 熱伝導性接着剤
1.はんだ代替接着剤の組成
1.1充填剤(フィラー)
1.2バインダー
1.3希釈剤
1.4添加剤
2.はんだ代替接着剤の特性
3.はんだ代替接着剤の機能
3.1保存安定性・作業性
3.1.1ストレージライフ
3.1.2ポットライフ
3.1.3印刷性、塗布性
3.1.4印刷時の粘弾性変化
3.1.5常温戻しと印刷時の温度管理
4.はんだ代替接着剤の特性
4.1接合強度
4.2熱伝導率の測定
4.3高熱伝導用導電性接着剤
4.4はんだ代替接着剤の高周波特性測定
4.5高周波対応はんだ代替接着剤
第8節 熱伝導性ゲル
1 ゲル
2 熱伝導性ゲル
2.1 熱伝導性ゲルの形態
2.1.1 シート状熱伝導性ゲル
2.2.2加熱硬化型熱伝導性ゲル
2.2.3 ペースト状熱伝導性ゲル
2.3 熱伝導性ゲルの設計
2.3.1 ベースゲル
2.3.2 熱伝導性充填材
2.3.3 その他の要求される特性
2.4 熱伝導性ゲルの多機能化
2.4.1 防振・緩衝特性 2.4.2 電磁波吸収特性
第9節 熱伝導性シリコーングリース
1.熱伝導性シリコーングリースの構成
1.1シリコーンオイルの種類及び特性
1.2熱伝導性フィラーおよび添加剤の種類
2.熱伝導性シリコーングリースの性質
2.1特性例
2.2主な特長
3.熱伝導性シリコーングリースの主な用途
4.熱伝導性シリコーングリースの塗布法
第10節 熱伝導性PCM
1.PCM(フェーズチェンジマテリアル)の概要
1-1.放熱材料の概念
1-2.PCMの装着方法
1-3.特性に影響するフィラー及び樹脂の諸因子
2.PCMの熱特性についての優位性
3.デンカフェーズチェンジ
3-1.デンカフェーズチェンジについて
3-2.実装評価
3-2.信頼性
第11節 高熱伝導半導体封止材料
1.樹脂の高熱伝導化と熱抵抗
2.高熱伝導性封止樹脂の設計
3.高熱伝導性フィラー
4.フィラーの高充填化
5.高熱伝導性封止樹脂における技術的課題
6.製品への適用
第12節 ポリエステル樹脂複合材料の高熱伝導化
1.開発の背景
2.新規な不飽和ポリエステル樹脂とその低収縮化
3.スーパーポリエステルRSPシリーズ
4.スーパーポリエステルRSP-7000
5.スーパーポリエステルRSP-9000
第5章 熱伝導性ポリマーの分散性評価
<本章の趣旨>
熱伝導性ポリマーにおけるフィラーの分散性評価手法について紹介す
る。具体的には熱伝導性に及ぼすフィラーの物理的性質や化学的性
質に注目し、フィラーの特性因子と複合材料の巨視的特性の関連性に
ついて熱伝導性粉体であるアルミナを例にとり、粉体の表面処理、粒
子径、粒度分布の観点から検討する。
1.熱伝導性の及ぼす要因 2.熱伝導性フィラによる複合効果
3.熱伝導性フィラの分散状態評価
3.1 顕微鏡法
3.2 X線マイクロアナライザー法
3.3 超音波法
3.4 原子間力顕微鏡
3.5 測色計
3.6 レオロジー的性質
第6章 複合材料の熱伝導性評価
第1節 場合に応じた効果的な測定方法
1. 高熱伝導プラスチックの特徴
2.複合材料に基因する問題点(有効熱伝導率の測定をめざす)
3.比較的大きな試料の熱伝導率の測定
4.小さな試料の熱伝導率の測定
5.実用的な測定方法
第2節 定常法
1.熱伝導率測定の基礎
1.1熱伝導率の定義
1.2 一次元定常熱伝導と測定概念
2.定常法による熱伝導率測定
2.1 測定法の種類
(1)保護熱板法
(2)熱流計法
2.2 測定上のポイント
(1) 定常状態
(2)試料の寸法
(3)移動熱量
(4)温度差
(5)試料の状態
3.幾つかの複合材料の熱伝導率特性
4、試験機関、市販の装置、標準物質及び測定装置の試作
4.1 試験機関、市販の装置、標準物質
(1)試験機関
(2)市販の測定装置
(3)熱伝導率の標準物質
4.2 測定装置の試作のすすめ
第3節 非定常法
3-1.熱線法および面加熱法(Hot disk法)
1.定常、非定常について
2.測定原理
2.1熱線法の場合
2.2Hot Disk法の場合
3.熱拡散率αの決め方
4.面熱源のHot Diskへの応用
5.Hot Diskセンサの構造
6.試料サイズとプローブ深さ(Probing Depth)
7.熱線法とHot Disk法との比較(相似則)
8.試料のセッティング、測定
3-2.レーザーフラッシュ法
1.レーザーフラッシュ法の概要 2.レーザーフラッシュ法の測定原理
3.レーザーフラッシュ法の測定精度を向上させる方策
4.複合材料の種類と伝熱工学上の問題点
5.分散系および繊維系複合材料にレーザーフラッシュ法を適用する
ときの条件
6.巨視的に不均質な複合材料の非定常問題
3-3.周期加熱法
1.原理
2.acカロリメトリを用いる距離変化法
2.1.金属薄膜の熱伝導率 2.2.超格子材料の熱伝導率
2.3.カーボンファイバーの熱伝導率
3.acカロリメトリを用いた薄膜材料の面に垂直方向の熱拡散率測定
-

- 和書
- 続・近くの山で出会う花