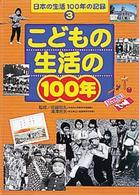内容説明
英国の手による植民地化と、ケニア独立を二つの突出した変化のピークとして展開されてきた、キプシギス社会の現代史。政治環境が激変する一連の過程で、キプシギスの人々は、国家的な中央集権政府による統治に対して頑強に抗いつつ、一方ではその統治制度を徐々に咀嚼・受容して、ついに現在の姿に至る実に大きく劇的な社会と文化の変容を導いた。では、彼らはそれをいったいどのようにして遂げたのだろうか。39年間、38次にわたって現地参与観察調査を続けてきた筆者が、錯綜する現実の諸事象から一貫性のある展望を切り開くための基盤作りを目指して、“人類学的思考”の翼を縦横無尽に羽撃かせる。
目次
「統治者なき社会」研究の展望
第1部 言語と民族・国家(スワヒリ語による国民形成と植民地近代性論―その可能性と不可能性をめぐって;キプシギスの殺人事件から見た国家と民族)
第2部 行き交い、ぶつかり合う時間と時代(マサイのビーズの腕時計―或いは、ユートピア思想のワクチン;走りそびれたランナーたち)
第3部 老人の権力―「統治者なき社会」はあるか(挨拶・握手行動の身体論と政治学;通過儀礼としてのイニシエーションの論理)
著者等紹介
小馬徹[コンマトオル]
1948年、富山県高岡市に生まれ。一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。大分大学助教授、神奈川大学外国語学部教授を経て、現在神奈川大学人間科学部教授。文化人類学・社会人類学専攻。1979年以来、ケニアでキプシギス人を中心とするカレンジン民族群の長期参与観察調査を三八度実施、現在も継続中。『川の記憶』(田主丸町誌第1巻)(共著、第51回毎日出版文化賞・第56回西日本文化賞受賞)1996、『日向写真帖 家族の数だけ歴史がある』(日向市史別編)(共著、第13回宮崎日々出版文化賞受賞)2002を初め、日本の民族や地方史など、人類学以外の諸領域の著述も数多い(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。