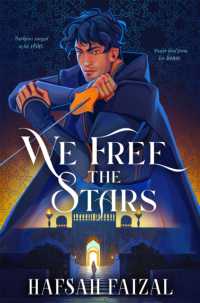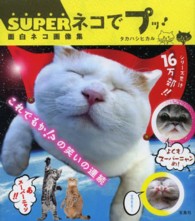出版社内容情報
◇子どもにとって「家族に替わる存在はない」けれど、代替するに値するだけの「愛」の存在を信じ続けて行動してきた民間の養護施設「光の子どもの家」19年の記録。
◇いま養護施設入所のほぼ全てが親の虐待を被けた子どもたちであり、「児童虐待防止法改正法」(2002年11月)の施行にもかかわらず、虐待を被けた子たちの受け皿として児童養護施設は、人が足りない、対応方法も手探りの野戦病院化している。
◇今何よりも、子どもたちに豊かな心の生活を与えられる「家族の力量」と、家族から切り離された子どもたちを「受けとめ」て、育むことのできるような「社会の力量」が問われている。
◇「光の子どもの家」の経験の記録は、今を生きる全ての子どもたち、これから生まれてくる全ての子どもたちにとって、養育の大切な参照の経験となっている。
【書評】芹沢俊介氏「十代にいたるまでの年齢の子どもがまず学習しなければならないことは、どんなことがあったとしても、決して断ち切られることなどない人との関係であると著者は述べる。つまり、『隣る人』の獲得だ」「①養護施設の見習うべきは、親子関係にみられる偏愛である。②情緒の涵養を第一義に、約束ごとを可能なかぎり少なくする。③養護施設は男がいなくても成り立つが、女が一人もいなくては成り立たない。④親の行方は手を尽くして追求する」「光の子どもの家の実践は、核を失った現代日本の家族関係を鮮やかに照らし出しているのである」(『週刊朝日』2003-4-4号)
【主な内容】
Ⅰ 「光の子どもの家」の家族とともに
はじめの一歩~光の子どもの家開設一〇年を経て/家族1(家族という情緒・則幸のこと・柴田さんの自殺・信夫・祥子と父の死)/家族2(年末の風景・帰る場所・偏愛のすすめ)家族3(協力・思春期真っ只中・寄る辺)/家族4(山下ファンド・尚一のこと)/家族5(暮らし・共に担う者・うわさ・言葉)/家族6(かけがえのない一人・新しい家族像・自立をかちとる訓練)/自立(高山嬉の場合・ホントウの〈自立〉・入野隆の場合)/信じる/関係/真実告知
Ⅱ 『光の子』初期通信
狭い門から/悲しんでいる人たちは/心の貧しい人々は/柔和な人々は/義にかわく人々は/憐れみ深い人々は/心の清い人々は/平和をつくりだす人々は/かがやきあう/お祭り/かわる/辞める/意欲/伝える
Ⅲ はたらくということ
はたらく(居会う・一緒に走る)/はたらくことと居ること/人になる/子どもをまもり育てる/「措置変更」ということ/子どもに関わる/愛される/暮らしの中で/小舎制養育の流れ/四天王プラス一/彷徨/出会い/私に与えられたもの
Ⅳ 出発(たびだち)
出発1~急がないで/出発2~隣る人/出発3~共に生きるということ/出発4~萌季のたびだち(萌季が出発つ・真実告知・世代間伝達の超克・祝いとしての日常・思春期・ 決意・労働権と生活権・子どもの権利擁護・自己受容1・アメリカ留学・自己受容2・プライバシー・自己受容3・利用する子どもたちは・自立)/あとがき
【BOOK著者紹介情報】
・菅原 哲男〈スガワラテツオ〉
1936年、秋田県羽後町生まれ。青山学院大学物理学助手・婦人保護施設「いずみ寮」、児童養護施設「城山学園」「愛泉寮」を経て、1985年に「光の子どもの家」を設立。施設長を務める。聖学院大学・足利短期大学講師。
内容説明
虐待を被けた子どもは、いつか大人になって自分の子どもを虐待する親になる!―そんな常識化した負の連鎖を乗り越えるために。子どもを受けとめる「家族の力量」「社会的養育の力量」がいま問われている。家族の愛に等しい養護をめざした「光の子どもの家」十九年の記録。
目次
1 「光の子どもの家」の家族とともに(はじめの一歩―「光の子どもの家」開設一〇年を経て;家族 ほか)
2 『光の子』初期通信(狭い門から;悲しんでいる人たちは ほか)
3 はたらくということ(はたらく;はたらくことと居ること ほか)
4 出発(急がないで;隣る人 ほか)
著者等紹介
菅原哲男[スガワラテツオ]
1939年、秋田県羽後町生まれ。青山学院大学物理教室助手・婦人保護施設「いずみ寮」、児童養護施設「城山学園」「愛泉寮」を経て1985年、児童養護施設「光の子どもの家」を設立。施設長を務める。聖学院大学・足利短期大学講師
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
しいたけ
megumiahuru
ツキノ
gami
すずめ
-

- 和書
- 最新ポーセレンテクニック