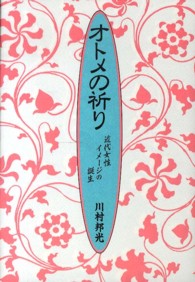内容説明
街道を翔け抜けた人馬たち―江戸時代に手紙やモノはどのように運ばれたのか。飛脚の知られざる全容に迫る、初めての書!
目次
第1章 「飛脚」誕生の歴史
第2章 列島をめぐる江戸期の飛脚
第3章 三都の飛脚問屋
第4章 飛脚ネットワーク
第5章 飛脚問屋と奉公人たち
第6章 輸送システムと飛脚利用
第7章 飛脚の金融機能
第8章 ニュースを伝える飛脚
第9章 飛脚事件簿
第10章 幕末維新期の飛脚
著者等紹介
巻島隆[マキシマタカシ]
1966年、東京生まれ。地方紙記者。放送大学卒業、信州大学・群馬大学大学院修士課程修了、高崎経済大学大学院博士後期課程修了。2010年、高崎経済大学博士(学術)。博士論文は「近世における飛脚問屋の研究―情報・金融・流通・文化の地域間交流」。2008年、石川薫記念地域文化賞(奨励賞)受賞。2014年、群馬大学社会情報学部非常勤講師(前期)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
黒豆
3
時代劇で文書のやりとりが出てくるが、それを担った飛脚の成り立ち、組織、所要日数、代金等に興味を持って読んだ。平安末期の合戦が飛脚を生み、鎌倉期の二元体制(鎌倉,京都)が飛脚を存続させ、室町期における治安の悪化が飛脚の活躍を促した。江戸-京都3日、京屋の取次所240箇所、手紙だけではなく、火災、水害、地震情報伝達も行い重要な組織だった。明治になり前島密は飛脚問屋の郵便事業への組込みを認めず、飛脚は日本通運へ、最近日通のペリカン便がゆうパックへ移行など興味深い内容だった。2015/04/23
ソウ
2
とにかく飛脚を様々な観点から論じた労作。前半は、古文書を紐解きながら、由来や店の種類・運用方法・日限・料金・利用者について。平安末期の合戦が増えた頃に飛脚という言葉が頻出するようになる。従来あった運搬屋「脚力」の「脚」と、早さを表す「飛鳥の如し」の「飛」に由来すると筆者は推測。後半は、金融や災害・戦争情報の伝達等その機能について。大金を実際に移動しなくて済むように発達した為替、細かく厳しい日限設定、近松門左衛門「冥途の飛脚」等。2015/03/12
伊達者
0
江戸時代の飛脚についての詳しい本。問屋や輸送ルートに関する細かいデータも収録されており,専門性も高い。コラムを挟んで柔らかいエピソードも取り上げられているのだが,少し専門性が高くて私には読みにくいところもあった。飛脚の業務の幅広さと重要性がぼんやりと分かった。2021/09/23