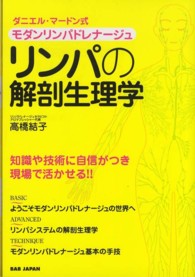内容説明
ブンデスリーガ史上最年少監督はなぜ勝ち続けられるのか。勝利を手繰り寄せる指揮官の哲学を解き明かす!チームを束ねるマネージメント手法から常に新しいものを取り入れる感性まで、ピッチ外での哲学、価値観など、ナーゲルスマンの“人間力”も徹底解剖!
目次
第1章 戦術的原則(最小限の幅;ウイングバックがゴール前で「ジョーカー」になる;止めて蹴るの「2タッチ」を心がける ほか)
第2章 指導・人生の原則(マネジメント;ブランディング;自己研鑽 ほか)
第3章 原則の実践―バイエルン1年目の成果と誤算
著者等紹介
木崎伸也[キザキシンヤ]
1975年生まれ。2002年にオランダへ移住してスポーツライターの活動を開始。2003年からドイツに6年滞在し、欧州サッカーや日本代表についてfootballistaやNumberなどに執筆してきた。取材で得た知識を生かし、2018年10月から本田圭佑率いるカンボジア代表のビデオアナリストを務め、2019年東南アジア競技大会では同国史上初のベスト4進出を果たした(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ルート
13
ナーゲルスマンの前に人数をかける戦術がすごい。ウイングバックがジョーカーとして、あらゆる能力を必要とされる。イタリア代表が2大会連続でワールドカップを逃していることから、カテナチオは第一戦ではそぐわない戦術になってきたのかな。カタールワールドカップではどんな戦術が一世を風靡するのか。2022/11/08
うえ
4
プレスの基準について。「ナーゲルスマンは次のようなアクションをトリガーにし…CB同士の距離がある程度離れていて、横パスが出された時。相手CBが前に大きくトラップした時。GKへのバックパス」とはいえこれら凡てへのプレスでは体力が持たないため、選手判断になると。とはいえFW個人が判断するプル型、後方の選手が指示を出すプッシュ型があり「両方使いこなすのが理想だ。」ここがかなり難しそうではある。浦和のゲーム等では、果たして的確な指示出し役がいるのかという問題もあるのだが。2025/07/18
Yanabod
4
現代サッカーの先鋭的な監督であるナーゲルスマンの考えを木崎さんが52の原則に落とし込んで、サッカー観戦者にもわかりやすい内容となっております。理にかなった発想に驚く一方、やはり最後は人が行うものなので、人心掌握の難しさというものを感じました。2022/08/15
多分、器用です
2
これはめっちゃ面白いし現代サッカーを見るのに役立つ2023/02/11
zepe(第1刷発行)
2
興味深い。 クライフのオランダ代表とペップバルサの戦術の基本的な考え方、特にボール狩りについて、インプットがある状態で読むと面白さがわかりやすいと思う。2022/10/30