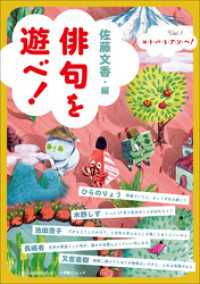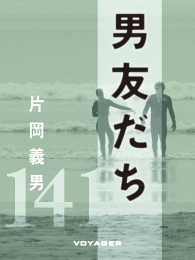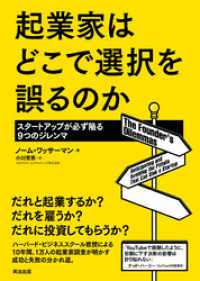内容説明
多くの生きものたちが姿を消しつつある日本の沿岸域。すべての生きものの「ふるさと」である海に、深刻な影響を及ぼし続けている人間の営み。かつて「宝の海」と呼ばれ、今では瀕死の状態となった有明海こそは、そうした日本の縮図である―。水際環境の保全と再生という喫緊の課題に向け、森と海の“つながり”、自然とともに生きる価値観の復元を目指す森里海連環の考え方に基づいた、研究者と市民協同による実践の成果を問う。
目次
第1章 筑後川流域から有明海再生を(瀕死の海、有明海の再生―森里海連環の視点と統合学による提言;筑後川河口域は有明海の“心臓部”;干潟再生実験―有明海の腎臓・肺機能の活性化;有明海再生シンポジウム、三年間の軌跡)
第2章 陸の森と海の森を心の森がつなぐ第四回有明海再生シンポジウム報告(有明海再生への展望;山の森、海の森、心の森;韓国スンチョン湾に諌早湾、有明海の未来を重ねる;大震災を乗り越え、自然の環から人の和へ;有明海のアサリ復活を人の輪で;有明海の自然と漁の特徴―有明海と人の関わりを撮り続けて)
第3章 NPO法人「SPERA森里海・時代を拓く」の誕生(メカジャ倶楽部からNPO法人SPERA森里海・時代を拓くへ;NPO法人「SPERA森里海・時代を拓く」の目的と思い;世代をつなぐ森里海連関に未来を託す;有明海再生におけるNPO法人の役割―漁師の期待)
第4章 瀕死と混迷の海・有明海再生への道(アサリの潮干狩り復活祭りに未来を託す;森里海連環による有明海再生の展望―もう一つの提言)
著者等紹介
田中克[タナカマサル]
京都大学名誉教授、公益財団法人国際高等研究所チーフリサーチフェロー、NPO法人SPERA森里海・時代を拓く理事。専門は水産生物学。有明海特産種稚魚やヒラメ、カレイ稚魚の汽水域における生理生態研究を通じて、「森里海連環学」という新たな統合学問領域を提唱している。2013年度、アカデミア賞(文化・社会部門)受賞
吉永郁生[ヨシナガイクオ]
鳥取環境大学教授、NPO法人SPERA森里海・時代を拓く顧問理事。専門は海洋微生物学、微生物生態学。特に、窒素の循環に関わる水圏の微生物の分子生態学を進める。琵琶湖、瀬戸内海、筑後川―有明海水系、気仙沼舞根湾(震災後の海洋環境)の基礎生産を担う細菌や微細藻などの研究に取り組む(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。