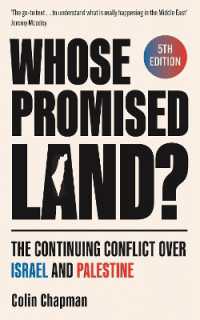- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
内容説明
気仙沼に生まれ、育ち、被災した民俗学者が地震・津波の状況と三陸沿岸の生活文化を語る。人間と海との強いかかわりを探り、真の生命を取り留めえる「復興」を示す。
目次
序 流されたものたちへ―家・母・漁港・漁村
1 津波をめぐる生活文化(津波と伝承―山口弥一郎『津浪と村』をめぐって;流された漁村に立つ;浸水線に祀られるもの;体に刻まれた記憶;三陸の漁師と津波)
2 三陸沿岸の生活文化(黒潮の果てから;気仙沼漁港の「みなと文化」;熊野漁民の東日本出漁;海から見えた山の神―東北太平洋岸の漁師の信仰;『遠野物語』を海から読む;漁師と「寄り物」;漁師の呪術観―気仙沼市少々汐、尾形栄七翁の伝承)
著者等紹介
川島秀一[カワシマシュウイチ]
1952年生まれ。宮城県気仙沼市出身。法政大学社会学部卒業。博士(文学)。東北大学附属図書館、気仙沼市史編纂室、リアス・アーク美術館等を経て、神奈川大学特任教授。日本常民文化研究所研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さな
1
放送大学「災害社会学」で紹介されていた本。著者は気仙沼出身の民俗学者。第1章と第2章の、災害にかかわる部分を中心に読む。p102の「津波を含めた多くの災害と共に歴史を刻んできた、この列島の人々の災害観や自然観をまずは認めることで、さらに防災や減災の計画を立てていかなければならないだろう」の一文に強いメッセージがある。この少し前のページの荒浜の話も含め、そこに生きる者たちが津波を受け入れてきた生活文化、精神文化をないがしろにした復興はあり得ないということだ。3章は三陸の漁業に関する民俗学の内容なので割愛。2024/02/06
yyrn
0
気仙沼に生まれ育った民族学者が、被災地の状況やこれまでに研究した三陸の漁村生活の文化や風習を語っている本。二度と同じ津波災害を繰り返さないために必要な備えとは何か。民族学者的な考察から、海と漁師を離すべきではない、高台移転は文化を断ち切ると語るが、為政者には云えないセリフだろう。ただ、過去の津波被災はいずれも他所者が来て復興を果たしたという言伝えを紹介していて、なるほどと思ったが、ただ漁業が今の時代でも魅力ある産業か?漁業以外で海辺に住みたいと思う理由が何かほかにあるだろうか? 2013/05/23
ekura
0
民俗学は科学ではない、文学だ、と揶揄されることがあるが、ある意味では的を射ている。ひとの人生に向き合ういとなみは、文学たらざるを得ないからだ。2018/12/11
-
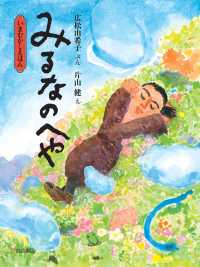
- 電子書籍
- みるなのへや いまむかしえほん
-
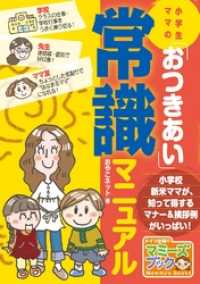
- 電子書籍
- 小学生ママの「おつきあい」常識マニュア…