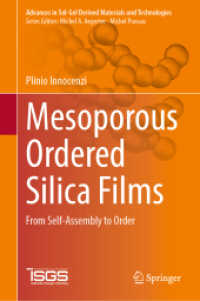- ホーム
- > 和書
- > 文庫
- > 学術・教養
- > 学術・教養文庫その他
内容説明
学生たちと読み解く夏目漱石『夢十夜』の世界。書き下ろし300枚。驚きの想像力を発揮する学生たちと教師・高山宏との白熱コラボレーションが、漱石研究へ新たな一石を投じる。
著者等紹介
高山宏[タカヤマヒロシ]
1947年、岩手県久慈市生まれ。現在、明治大学国際日本学部教授。1968年刊行の『観念史事典』に魅了され、学の行き詰りがどういう感覚のどういう人々によって突破されるかの構造と歴史を追うのに夢中となり、結果的に領域横断的試みを続けるもの書きの一人となる。翻訳の質量は伝説的で、本人自身は翻訳家、最近はアート(Art/Ars)の人としての自覚が強い。別名学魔。著訳書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ケイ
138
自分で漱石の夢十夜を読むと、どうしても一気にいってしまうのだが、解説が入ると、一話一話をゆっくりと味わう時間があった。実際に、3週間かけて読んだ。学生の書く感想もそれぞれで面白い。私はもともと第九夜が最も好きで、読むたびに涙がとまらなくなるのだが、それは今回も。この夜を一番好きだという人にはあまり合わないから、他の方の感じ方やいわゆる文芸評などをここで知れていい機会となった。そして最後の〆だからか、第十夜の怪しさに囚われ、ずっと豚たちのイメージが頭に残る。聖書の場面とともに。2017/02/02
コットン
71
『夢十夜』を文学だけでなく美術や文化など多方面からの分析により読み解く手腕にワクワクする!まずは第一夜、第二夜という数に意味がありつながりもあると…(『三四郎』など346と親友の小次郎546とか)、また鶏は道化を意味し無意識から意識へ超えていくシンボルだとか。2014/10/22
まこみや
22
『夢十夜』は、漱石の作品の中でも、とりわけ読み手に解釈や分析を強く誘う。しかしなかなかその正体を掴むのは難しい。高山宏氏のこの表象文化論の講義録は、様々な領域を横断しつつ、次々と鮮やかな手法や理論を繰り出してゆく。それはまるで達人の剣捌きか巧みな魔術師の手妻にも似て、快刀乱麻に未明を断つものだ。博覧強記の怪物高山宏にして初めて成し得る芸当だろう。同時にこの授業に参加してきた学生「同志」にも敬服する。漱石再発見の高山氏の思いは、私の中にも深い共感を波及させた。文芸批評の醍醐味を堪能した。2021/03/30
しずかな午後
12
『夢十夜』は夏目漱石の幻想的な掌編集。正直に言えば、本書を読むまで『夢十夜』は捉えどころのない、よく分からない話の集まりという印象があった。それを高山宏が、モチーフやディティールを手がかりに、明治という時代状況、近代の都市文化、ギリシャ神話等の西洋の古典文学、その他いろいろな美術・哲学・科学技術…へと展開していく。知識が次々に繋がっていくことの楽しさに溢れている。また、本書は大学で行なった講義の記録でもあり、受講者のレポートが引用される。それもライブ感があって良かった。2023/09/08
白義
12
夢十夜の、日本近代への眼差しや膨大な博識を詰め込んだ迷宮的な世界に分け入りながら、終わりなき解釈の連鎖に読者や学生を誘う名講義。夢十夜の各編も全文収録なのでここから入って問題なし。深読みの快楽が更なる深読みを導き、意味がどこまでも膨れ上がっていく。ロマン主義、バロック、マニエリスムと、高山ワールドいつもの概念が漱石の中のアンビバレンツモダンな部分に妖しく光を当てる。学生たちのレポートも相当出来がいい。高山宏本では明白な実践編かつコンパクトなので一息に読める。やっぱり三夜は怖いね2013/02/20
-
- 洋書
- Retribution
-
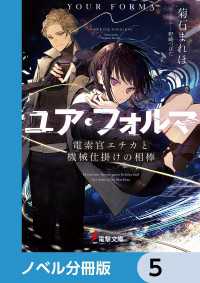
- 電子書籍
- ユア・フォルマ【ノベル分冊版】 5 電…