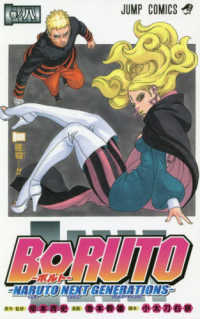内容説明
社会主義国家ソ連のアングラ社会に足を踏み入れたターニャはジャズ・ミュージシャンと人生の喜びを見いだしていく。孤独なエレーナは徐々に精神に異常をきたしていき、パーヴェルはもはや家族とのつながりを取り戻すことができそうにない。ばらばらになった家族を娘のターニャはもう一度ひとつに織り合わせることはできるのか…。若者文化が非公式の世界で活気にあふれていたスターリン死後の社会のなかで、生と死の問題がひとつの結末を迎える。ロシア・ブッカー賞受賞作。
著者等紹介
ウリツカヤ,リュドミラ[ウリツカヤ,リュドミラ] [Улицкая,Людмила]
1943年生まれ。モスクワ大学生物学部(遺伝学専攻)卒業。1980年代から小説を発表しはじめていたが、1992年に発表された『ソーネチカ』(沼野恭子訳、新潮社)がヨーロッパ各国ですぐに翻訳され、フランス(メディシス賞、96年)、イタリア(ジュゼッペ・アチェルビ賞、98年)で文学賞を受賞、国内より先に海外で高い評価を受けた。ロシアでは2001年に『クコツキイの症例』でロシア・ブッカー賞を受賞、現代ロシアを代表する女性作家
日下部陽介[クサカベヨウスケ]
早稲田大学第一文学部日本文学科卒、同大学院文学研究科ロシア文学科修士課程中退。その後、国際交流基金に入社。現在は在ロシア日本大使館に出向し、三度目のモスクワ勤務中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
キムチ
43
激しく読み辛くて呻吟した2章を経ての3章は飛躍的に面白く、すいすい。情景、人々の歩みや想いが受けとめられた。4章となり、ターニャの在り様は流石というか。奔放を超えて、ロシア的というか。性を本能優位で扱い、結婚も然り。妊娠しても、愛人と激しい行為で明け暮れる。周囲は・・なんて思うのはがちがち日本人だからかと自省(笑)しかし、最後の審判が。ターニャがそうなったのは歯車の最も悪いかみ合わせでなるべくしてなったのか。洋画のシーンによくある結末。ウリツカヤから言わせると人生のドラマはちょっとした匙加減で。かな?2022/02/24
ふみ
16
このあらすじというか、惹句というか、間違ってないけど間違ってるよな、と間抜けな感想を抱きつつ、人間そう簡単には不幸になれないと実感する。2016/06/17
erierif
10
夫婦の根本的なところに問題があるのだけど、若者の話で散漫になってしまいなにか物足りないまま終了したようだった。しかし、後書きに訳者が「クコツキイ家の人々」にしようとして断られたとあったのが興味深い。トルストイがちらちら出てくる。「幸福な家庭は似ているが不幸な家庭はそれぞれ違っている」という名言を思い浮かべながら読んだ。ゆえに症例(ケース)というタイトルにしたのかななど深読みできたり、ありきたりの年代記とは違う読後感だった。2013/11/04
ハルト
3
読了:○2013/10/13
ひとみ
3
大学をやめ奔放な生活に飛び込むターニャ、心身を病むエレーナ、アルコールに溺れるパーヴェル…幸せだった一家は崩壊寸前だったが、ターニャの奇妙な結婚と妊娠出産を機に歩み寄ろうとするのだったが…。戦争からスターリン体制下、新しい文化の入ってきた20世紀前半のソ連とある奇妙な家族の姿を通じて描いた小説。歴史にSFやマジックリアリズム的な手法に生命に関する問や青春小説のような要素もあって全体像を見通すのは難しかったけれど、著者特有のユーモアに読むのを助けられた感じでした。2013/10/05