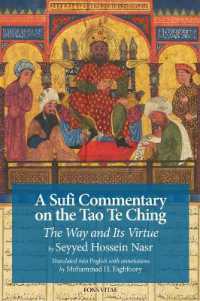出版社内容情報
徳川日本において、どのように自己像が生起し、近世帝国的普遍性を切り裂くのか。また国境認識はどのようにして現れ、他者認識を生み出していくのか。グローバリゼーション下でむしろ高まりつつあるナショナリズムの源流を、東アジアへ視線を向けるなかから探り出し、近代の学術がそれをいかにして制度化していったのかを解明する。
はじめに
第一章 一八世紀の自他認識
――宣長の「外部」――
第二章 華夷思想の解体と自他認識の変容
――一八世紀末期~一九世紀初頭期を中心に
第三章
内容説明
徳川日本において、どのように自己像が生起し、近世帝国的普遍性を切り裂くのか。また国境認識はどのようにして現れ、他者認識を生み出していくのか。グローバリゼーション下でむしろ高まりつつあるナショナリズムの源流を、東アジアへ視線を向けるなかから探り出し、近代の学術がそれをいかにして制度化していったのかを解明する。
目次
第1章 一八世紀の自他認識―宣長の「外部」
第2章 華夷思想の解体と自他認識の変容―一八世紀末期~一九世紀初頭期を中心に
第3章 一国思想史学の臨界点―帝国日本の形成と日本思想史の「発見」
第4章 国学への眼差しと伝統の「創造」―「想像の共同体」と国学運動
第5章 東アジアの近代と「翻訳」―近世帝国の解体と学術知
第6章 現代日本のナショナリズムと「教科書問題」
付論 東アジア人文学の可能性を求めて
著者等紹介
桂島宣弘[カツラジマノブヒロ]
1953年生まれ。立命館大学大学院文学研究科博士後期課程修了(文学博士)。現在、立命館大学文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。