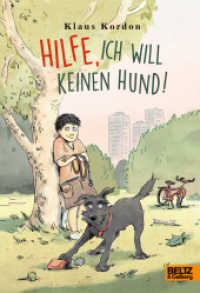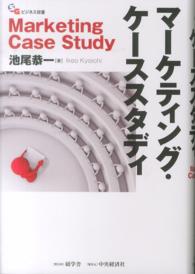出版社内容情報
これ1 台でギターの練習から作曲・アレンジまでOKという優れもののマシンがQY100です。曲が頭に浮かんだときにメモ代わりに使っているプロもいるほどの便利さと高機能。このマシンの使いこなしをイチから丁寧に説明しています。
リズム・マシンで色々なジャンルのノリを練習して、あっちこっちのバンドでセッションしているうちに、あるJ-POP シンガーの曲のバックのレコーディングに参加、それをきっかけに自分のバンドでメジャー・デビューしたという例もあるとか。そんな練習もこのマシンがあればOKです。
増補版ではさらに、自分でオリジナルパターンを作る方法やシンコペーションの入力方法、データファイラー活用法など一歩先行くQY 活用法を紹介。
昔はたくさんのCDを買いあさって、聴きまくってドラム・パターンを耳コピして頑張ったもの。今は、代表的なリズムがQY100にプリセットされています。さあ、活用法を本書でつかみましょう。
目次
まえがき
●Part 1 QYを使った練習法と作曲入門
■QYからバッキング・リズムを学ぶ
1.リズム感をQYで強化
2.素早くパターンを変えるワザ
3.ギター・パートをじっくり聴こう
4.ワン・パターンに陥らないために
【コラム】アレンジ逃げの一手
■QYを使ってスケール練習をする
1.煮詰まると、みんなでスケール練習
2.いつものスケールでも
3.こんなのラクショー~という方は
4.テンションを含んだスケール練習
5.ディミニッシュなんてコワクナイ
■QYのSONG 入門
1.いよいよ、SONG でコード進行入力
2.ソングモード
3.何を入力するのかでトラックを決める
4.パターンを先に入力
5.続いてコードを入力
6.1回で終わりじゃ……
7.JOB でコピー
【コラム】ギター用エフェクトについて
●Part 2 作曲もQYにおまかせ!
■コード・テンプレートで曲の母体を作る
1.コード・テンプレートとは?
2.クリシェ???
3.コード・テンプレートを選ぶ
4.プリセット・テンプレートを、
■ユーザー・エリアにコピーする
5.まずはイントロ
6.あっ! 間違えた! ど~しよ~……
7.MainA、MainB も続けてコピー
8.転調ワザ
9.そしていよいよエンディングだ!
【コラム】 「+1YES」「-1NO」ボタンか
■「SHIFT +黒いボタン」か?
■セクションを使う
1.パターンのセクションを入力する
2.表記上の注意
3.セクションで曲構成を入力
■メロディの入力
1.メロディは、どうすんだよ!
2.ステップでメロディを入力する
3.メロディはどこに?
4.画面の説明をしておこうかな
5.分解? 脳? エッ!?
6.画面右の4つのボタン
7.さあ、いよいよ入力だ!
8.ここでチョット確認
9.入力したメロディをコピーする
10.さて、次はサビ(MainB)の入力だ
11.ラクラク! コピー!
12.できたかな?
【コラム】リアルタイム入力について
【コラム】このパターン、あの曲じゃないの?
●Part 3 曲全体の調整(ミックスダウン)
■メロディの音色を変更
1.ミキサー画面を開く
2.音色の変更
3.新ワザ! SHIFT +「+1 YES」ボタン
【コラム】メモリーに関して
■エフェクト処理
1.エフェクトの調整
2.Effect Send
3.DELAY の設定
4.ちょっとしたワザ
■バックとメロの音量調整
1.最終音量調整
●Part 4 一歩先行くQY活用法
■自分でオリジナルパターンを作る方法
1.ユーザーパターンの選択
2.セクションと小説数の設定
3.入力設定
4.入力する音の確認
5.入力開始
6.入力設定
7.試聴してみよう
■シンコペーションの入力方法
■「OCT DOWN」「OCT UP」ボタンの第三の使い方
■データファイラー活用法
1.接続と設定
2.接続確認
3.QYに保存されている全てのデータを
■パソコンに転送する
4.バルクデータをQYに戻す
5.QYで作成したSong をコンバートしてパソコンに転送する
6.SMF をQYに送信する
【!】注意
おわりに
ただやみくもに練習したって、なかなかギターってうまくはならないでしょ?一人で部屋の中で黙々とギターを抱えて弾きまくって、さてバンドの練習日にメンバーとあわせてみても、一人では弾けた速弾きフレーズがバンドであわせてみると追いつかない……ちょっと難しいコード進行だとアドリブもままならない……メンバーに「カッティングのノリが悪い」と言われた……みんな多かれ少なかれ「……」となることってあるんじゃないかな?でもね、ちょっといつもの練習に工夫を加えれば「……」が解消されるはず。そう、QY100 があるじゃないか!これ1 台でギターの練習から作曲・アレンジだってOK! しかもデモ・テープまで簡単に作れちゃうゾ!
実際に僕もそうだけど、曲が浮かんだときのメモ代わりに使ってるプロも多いんだよ。プロの条件というのはいろいろあるけど、「幅広い音楽性を持っている」というのが一番なんじゃないかな。僕の友達にもロック一辺倒で、譜面もろくに読めないギタリストだったやつが、リズム・マシンでいろいろなジャンルのノリを練習して、あっちこっちのバンドでセッションしているうちに、あるJ-POPシンガーの曲のバックのレコーディングに参加、それをきっかけに自分のバンドでメジャー・デビューしたなんていう例もあるんだ。まあ、たくさんのジャンルを弾くことができれば、活動の幅が広がるし、チャンスもそれだけ増えるってことだよね。その友達はたくさんのCDを買いあさって、聴きまくってドラム・パターンを耳コピして頑張ってたけど、今は代表的なリズムがプリセットされたQYなんて便利なものがあるんだから、使わない手はないよね。とにかく、すごくたくさんの便利な機能を持ってるQY100 を使いながら、みんなの楽器(ギターだけじゃない、他のメンバーにも役に立つよ)の腕がプロ・レベルに近付くよう、そして効率的な作曲法、さらにセンスのいいアレンジができるように解説していくので、レベルアップを目指してガンバロー!
内容説明
これ1台でギターの練習から作曲・アレンジまでOKという優れもののマシンがQY100です。曲が頭に浮かんだときにメモ代わりに使っているプロもいるほどの便利さと高機能。このマシンの使いこなしをイチから丁寧に説明しています。リズム・マシンで色々なジャンルのノリを練習して、あっちこっちのバンドでセッションしているうちに、あるJ-POPシンガーの曲のバックのレコーディングに参加、それをきっかけに自分のバンドでメジャー・デビューしたという例もあるとか。そんな練習もこのマシンがあればOKです。増補版ではさらに、自分でオリジナルパターンを作る方法やシンコペーションの入力方法、データファイラー活用法など一歩先行くQY活用法を紹介。
目次
Part1 QYを使った練習法と作曲入門(QYからバッキング・リズムを学ぶ;QYを使ってスケール練習をする;QYのSONG入門)
Part2 作曲もQYにおまかせ!(コード・テンプレートで曲の母体を作る;セクションを使う;メロディの入力)
Part3 曲全体の調整―ミックスダウン(メロディの音色を変更;エフェクト処理;バックとメロの音量調整)
Part4 一歩先行くQY活用法(自分でオリジナルパターンを作る方法;シンコペーションの入力方法;「OCT DOWN」「OCT UP」ボタンの第三の使い方;データファイラー活用法)
著者等紹介
目黒真二[メグロシンジ]
東京写真専門学校(現・東京ビジュアルアーツ)音響芸術科卒。7年間のサラリーマン生活を経て1994年渡米し、MI(ミュージシャンズインスティテュート)ベース科に入学。帰国後、ベーシスト/ギタリストとして数々のツアーに参加。またフリーのPA/レコーディングエンジニア/シンセサイザー・マニピュレーターとして活動する傍ら、2000年よりDTM関連/楽器/機器のテクニカルライターとしても活動を始め、現在までに20冊を超える著書を発行、そして20本を超える教則DVDに出演、また雑誌「サウンド&レコーディングマガジン」、「サウンドデザイナー」などに寄稿している。また「平池尚」としてアレンジャー活動もしており、レーベル「ゴールデンカップ/セントラルレコード」のディレクターも兼任している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。