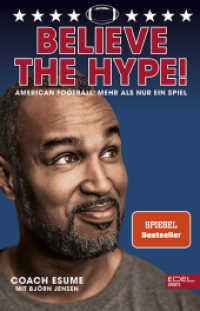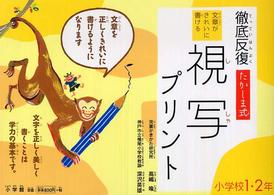内容説明
中国台頭を加速させその後の世界に大きな影響を与えた“アジア通貨危機”を舞台に国際政治経済の最深部を描く。世界経済の転機において、何が起きたのか。現代世界をより深く理解するための必須の書。
目次
第8章 泡と消え去る―インドネシア一九九八年一月~四月
第9章 突き付けられた「ニエット(ノー)」―ロシア一九九八年七月~八月
第10章 リスクのバランス―米国一九九八年八月~九月
第11章 どこまで深いのか―米国一九九八年九月~一〇月
第12章 ようやくにして脱出―ブラジル一九九八年一〇月~一九九九年三月
第13章 危機から脱したあとに
著者等紹介
ブルースタイン,ポール[ブルースタイン,ポール] [Blustein,Paul]
ジャーナリスト。1951年米国生まれ。オックスフォード大学で哲学・政治学・経済学を学ぶ(ローズ奨学生)。ジャーナリストになり、フォーブズ誌、ウォール・ストリート・ジャーナル紙、ワシントン・ポスト紙で、経済・ビジネス分野の記者として活躍。1990年~95年には、ワシントン・ポスト紙のアジア特派員として東京に赴任。経済・金融分野における卓越したジャーナリズム活動に贈られる「ジェラルド・ローブ賞」を含む、数々の賞を受賞。現在、ブルッキングス研究所フェローも務める
東方雅美[トウホウマサミ]
東京都出身。慶應義塾大学法学部卒、米国バブソンカレッジ経営大学院修士課程修了(MBA)。出版社や経営大学院の出版部門での勤務を経て独立。ビジネス・経済分野を中心に、翻訳、ライティングなどを行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
-
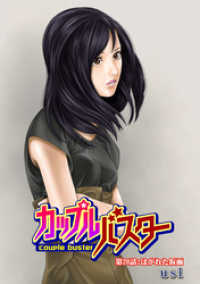
- 電子書籍
- カップルバスター 分冊版 20 アクシ…