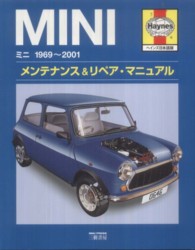内容説明
空気のように当たり前に届く電気。その安定供給を支える電力会社の仕事と魅力にたっぷり迫る。そこには、どんな時も電気を絶やせない緊張と達成感があった。路上の電線保守から原子力発電まで、あらゆる職種をとことん紹介。
目次
1 電気をつくるしごと
2 電気を届けるしごと
3 電気を販売するしごと
4 地域とつながるしごと
5 経営に関わるしごと
6 新しい分野に挑戦するしごと
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
超運河 良
7
消費者が製品やサービスを一度購入したら以後使わざるを得ない付属のサービスがついてるビジネスは売り手が強くなる。携帯電話という本体を作って販売店に卸すよりも、電波を繋げる方が長期的な収益と固定収益を同時に得る事ができる。電気も発電所も大事だけど、送電網という線を保有している方が価格決定権と地域独占力を容易に握る事ができる。発送電分離をしたとしても、送電専門の会社は消費者の流通網が強いので、価格転嫁や修繕維持の設備投資は少なくて済むので、一貫して高利益率になる。ビジネスは消費者の流通網が強い方が長期的な競争力2015/08/26
ksdr0000
3
電力会社の仕事全体を広く浅く解説した本。電力会社への就職を希望する文系の学生向けの内容と感じた。突っ込んだ内容は乏しい。東日本大震災によって原子力発電の評価が大きく変わり、本書の内容が通用しない部分も多いので更新版がほしい2014/06/23
スカ
2
電力会社の全体の取り組みと必要としている人材がわかります2010/03/26
銀雪
1
ブックオフで購入。2009年刊なので、3.11や電力自由化についての記載はなく時代を感じる。配電設備や送電線についてなど、業界の基本を学ぶ参考になった。「高温超電導ケーブル」については、今どうなっているのか調べてみたい。これの、情報が新しいものは出ていないのだろうか。2025/04/13
asagiri_co25
1
部門・部署ごとに電力会社の仕事についてインタビュー的に解説した本。業務内容だけでなくその部署に就くために必要な学習分野や、やりがいについても重点的に書かれている。大企業の部門構成がどうなっているかについても参考になるかもと感じた。また、「安定供給に火力や原子力は欠かせない」という見方があり、旧一電の電力供給に対しての考えが垣間見えるところがあった。また出版年が2009年と古めのため、今後のエネルギー構成などが今の政策と合わないところあり。2021/05/05
-
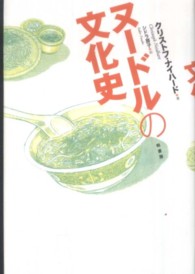
- 和書
- ヌードルの文化史