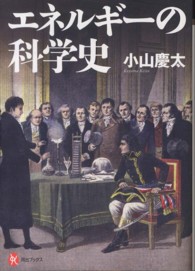目次
1 写真 帰還困難区域とその周辺
2 フクシマの声(避難、そして長き不在;記憶の中のふるさと;生きるという事)
著者等紹介
菊池和子[キクチカズコ]
1945年中国石門市(現河北省石家荘)生まれ。東京学芸大学卒業後、東京都公立小学校教諭となる。48歳のときから夜間の写真学校で学ぶ。54歳で教職を辞し、ポルトガル・リスボン市で6年間暮らす。2008年に帰国(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ベル@bell-zou
25
防護服なしで入れない我が家。汚染土の黒い袋の山の異様な光景は心を暗くする。2016~17年にかけ著者が聞き取った、福島の避難指示・帰宅困難区域の人々の声。特別養護老人ホーム「サンライトおおくま」の過酷な避難過程。救いの手は国ではなく同業他地域の老健施設。公表する数字により隠蔽される甲状腺がん発病の実態。情報の遅さと少なさが人生ごと奪われた人々を更に苦しめる。隣県の原発事故にも関わらず現状を知る機会が少なく感じ手に取った。2018年1月初版の本書、既に「書庫」貼付。放射能に県境は無いのに複雑な思いがした。2019/03/09
けんとまん1007
22
つくづく思う。こんなに理不尽なことは、あってはいけない。それにもかかわらず、もう過去のこととして、振り返ろうとすらしない輩の、何と多いことか。それどころか、意図的に、葬り去ろうとすらしているではないかと思ってしまう。政官財学のとめどない癒着の構造にすくっている輩だ。自分たちは、一人の人間として、忘れてはならないのだ。オリンピックだの、万博だのと、それに騙されてはいけない。2018/11/24
timeturner
10
東日本大震災後から現地の写真を撮り人々の話を聞いてきた著者が、7年後、故郷を奪われた人たちの一時帰宅に同行し、ひとりひとりの「あの時」「その後」についてを聞き書きしたもの。「被災者」という抽象的な概念でなく、固有名詞をもちそれぞれの生を生きる人々の話は心に刺さる。ごく普通の何も悪いことをしていない人たちがこんな運命を背負わされ見捨てられていいわけがない。2018/10/14