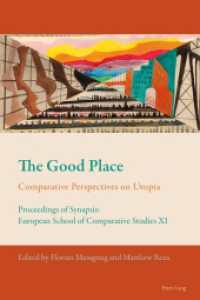内容説明
熱、電気、そして原子力の発見は、人類のエネルギー観をどのように変えたのか。19世紀から現代に至るエネルギー開発と活用の歴史を、アインシュタイン、ボーア、フェルミ、朝永振一郎ら歴代の科学者を軸にたどる。自然を理解し、宇宙を認識するという科学の営みは、煎じ詰めればエネルギーの正体とそれによって生起する諸現象の解明に尽きるといえる。エネルギーと社会の関係が再考を迫られている今、近視眼的なエネルギー論争で見失いがちな問題の本質に迫る野心作。
目次
序章 エネルギーの歴史の分水嶺
第1章 蒸気機関と熱エネルギー
第2章 電磁気学の確立と電気エネルギー
第3章 放射能と原子核―新しいエネルギー
第4章 核エネルギーの解放
第5章 ミクロの世界を操るエネルギー
第6章 宇宙と暗黒エネルギー
終章 エネルギー、過去・現在・未来
著者等紹介
小山慶太[コヤマケイタ]
1948年生まれ。科学史家。早稲田大学社会科学総合学術院教授。理学博士。専門は物理学、天文学の近現代史。早稲田大学理工学部卒業(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
110
エネルギーの科学史ということで最初の蒸気機関は第一次産業革命へとつながり、次の電機は第二次産業革命ということでかなりの産業の発展に寄与しています。その後は原子力によるエネルギー、また宇宙と暗黒エネルギーということでかなり専門的になってきています。ただ様々なエピソードなどが多く、一つの話も比較的短いので読みやすさはあります。2016/07/24
白義
15
エネルギーの科学史とは現代産業を支える根幹の動力の歴史であるというに留まらず、宇宙の根底にある力の探求の歴史でもある。原発論争などの以前にその根本的なエネルギー観、人とエネルギーの関わりを見直すために蒸気、電気、原子力、そして反物質やダークエネルギーとエネルギー研究史の画期たる場面をエピソード豊かに語っている。ガルヴァーニ電気の発見から電池の発明に至る数奇な偶然の連鎖、20億年前に存在した天然の原子炉の研究が揺るがすかもしれない物理定数の不変性問題など、科学史の面白さに満ちていて現代へのヒントにもなる良書2016/07/07
もなおー
9
面白かった。うまくまとまっているので、かなり読みやすかった。後半ちょっと急ぎ読みしすぎたから、後日またかな。内容としては大学教養課程+αくらいなので、ある程度物理をちゃんと勉強している高校生なら(時間はかかれど)読み切れるレベル。2016/09/14
猫
8
物理と科学から見出されてきたエネルギーの形の歴史。熱や電気の比較的わかりやすいエネルギーから、原子力などの大きすぎるエネルギー、はては宇宙を満たしている正体不明の暗黒エネルギーまで。わかりやすい言葉と読みやすい文章でなんとなくわかったような気にさせられるけど、基本がないので実際にはあまり理解できていなさそう。真空には何もないのではなく、負のエネルギーが詰まっていて、それは科学的にも実証されていると言われても「お…おぅ(困惑)」てなってしまう^^;2019/04/07
こだまやま
5
エネルギー利用の歴史から核融合の辺りまではなんとかついていけてたのだが、途中から加速度的に置いてけぼりにされ、反物質、ダークエナジーまで来る頃には最初とは違う本を読んでいるようだった。最終章で述べられているように、産業的な利用方法はエネルギーの一面にすぎない、エネルギーを考えることは宇宙の存在を説明することなのだという、筆者の壮大な意図を感じた。“変化“をもたらすものはすべてエネルギーなのだから。2025/01/25