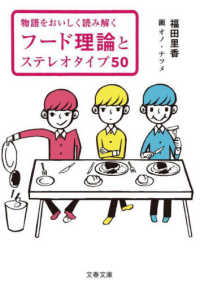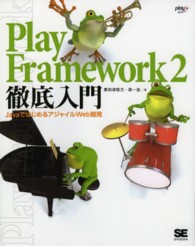目次
第1章 ケアの原風景を考える―救済としてのケア、死を思うケア、そして人格の統合と再生、そして調和の物語
第2章 ライフの視点とケアをめぐる言葉たち
第3章 ケアの基本原則と生活問題の構造的理解の方法
第4章 ケアの担い手の病理現象とは何か―バーンアウト・シンドローム(燃え尽き症候群)への理解
第5章 対象喪失とケアの方法―「喪(悲哀・悼み)」へのケアを考える
第6章 ケアの稽古論―援助技能が身に付くとは、どういうことなのか
第7章 シャーマニズムとケアの関係論―ケアの人類学を求めて
第8章 ケアの現場で生きること―ケアは深くて暗い迷宮から始まった
終章 ケアの寓話、そして、大切なもの
エピローグ ささやかな感謝と願いを込めて
著者等紹介
結城俊哉[ユウキトシヤ]
国立大学法人筑波大学大学院人間総合科学研究科人間系(障害科学域・障害科学専攻・障害福祉支援学分野)准教授。研究分野ケア論、ソーシャルワーク論、精神保健福祉学、障害者福祉学。最近は、災害ストレス及び対象喪失問題への支援と対人援助職へのケアを研究テーマとしている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ありたま
4
とてもよかった。序論とエピローグに書かれていた通り、ケアの本質的な、哲学的な概念から実践的な方法論、ケアに関する先人たちの考えなどが学べる良書だった。今まで漠然と考えていたことが明確に整理されていてとてもよかった。6章のシャーマニズムの話は知識が足らず理解が難しかったけど著者の民俗学的な考え方が伝わる面白い章だったな。芸事の「型」概念がケアの稽古論と結びつけられるのも興味深い。本筋とはずれるけど著者が芸事を「アート」という言葉で表現しているのも印象に残った。2023/08/14
ゆう。
0
とても難しい本でした。ケアとは何か、私たちのライフの視点から、様ざまな視点から分析されていました。また、バーンアウトやケアの現場で大切なことについても述べられていました。結城先生の論文や本は、独特な研究方法なので、僕は混乱することもあるのですが、ケアの原風景について考えるうえでは、面白い本だと思います。2013/11/02
オラフシンドローム
0
★★★★☆ 専門技能を稽古する方法について考える。 後半を中心に読んだので、また別の機会に読みたい、「ケア」について、物語やスピリチュアルやアートから論じた興味深い本。2025/05/17