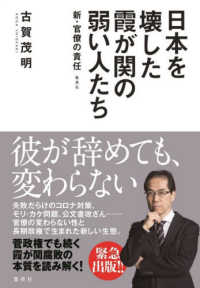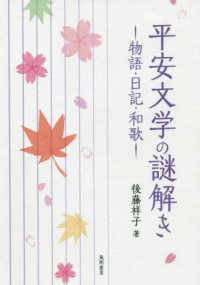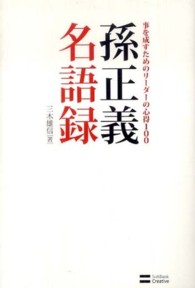内容説明
震災を超えて語られる“人間”と“言語”。ハイデガーの言葉、山村暮鳥の詩、ボブ・ディランの歌が問う。
目次
純粋言語論
山村暮鳥と萩原朔太郎
満州からハートランドへ―戦争詩論以後
伝道者ディラン
ハイデガー「言語」試訳と註
著者等紹介
瀬尾育生[セオイクオ]
1948年生まれ。東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了。現在、首都大学東京教授。著書に詩集『DEEP PURPLE』(高見順賞)評論集『戦争詩論1910‐1945』(やまなし文学賞)『詩的間伐―対話2002‐2009』(稲川方人と共著、鮎川信夫賞)等がある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。