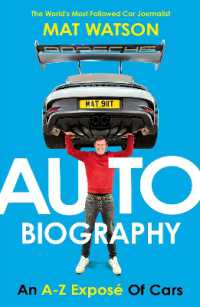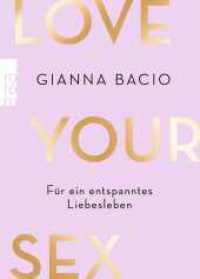出版社内容情報
ここに一つの試みとして、新約聖書の中の「福音書」すなわち《よきたより》と呼ばれてきた古代の書の新しい形式の翻訳を読者にお届けする。
これは一つの冒険であり、実験である。このような形式の翻訳は、これまで試みられたことがない。その目的は、一般の日本人にとってかなり難解であり続けた「福音書」を楽しく親しみやすく、わかりやすいものとしてお伝えすることである。「福音書」は、これを読む多くの人びとにとって、文字通り《よきたより》でなければならない。そのためには、この書の言わんとしていることが、読者の心に抵抗なく受け入れられ、共感と感動をもって理解される必要がある。訳者の試みはこの一点を目指す。(本書より) 本書の特徴
本書の特徴
・本文への補註の挿入
「福音書本文」と「註釈文」とを、文として一つながりになるようにしながら、註釈の部分を段落を下げ、字体を変えて、一目で見分けられるように書いています。これにより、補註をいちい参照しながら読む必要がありません。
・異文化の文物風俗の言い換え
新約聖書は現代の日本とは地理的、時間的、文化的にきわめて遠い二千年前の出来事を書いた文章です。日本人の生活文化からかけ離れている文物・動作については、本文の内容を損なわない限り思い切って変更し、日本的な表現に置き換えました。例:「接吻→頬ずり」「隅の親石→大黒柱」「紫の衣に柔らかい亜麻布→金襴の衣装に緞子の帯」など
・翻訳文体の選択
イエスの活動した二千年前のユダヤの社会は身分制度が厳しく、王があり、家臣があり、富裕な商人や地主階級のもとに自作農、小作農があり、零落した日雇いの労務者があり、奴隷がいました。こうした社会に似せようと幕末から明治維新のころの日本語を擬似的に用いることを試みました。
地の言葉「公用語」は関東武家階級の言葉に似せる。ガリラヤ出身のイエスとの仲間は東北地方の農民の言葉。イエスは仲間と喋るときは方言丸出しでしたが、改まったお説教をするときや、階級の上の人に対しては公用語を使う。さらに、ファイサイ衆は武家用語、領主のヘロデは大名言葉、イェルサレムの人々は京言葉。商人は大阪弁。サマリア人は山形県庄内(鶴岡)弁。ガリラヤ湖東岸の異邦人たちは津軽弁。ガリラヤ衆はケセン語や仙台弁、盛岡弁。イェリコの人は名古屋弁。ユダヤ地方の人は山口弁。ローマ人は鹿児島弁。ギリシャ人は長崎弁など、全国各地の多彩な方言が飛び交います。
目次
第1巻 マタイの伝えた“よきたより”
第2巻 マルコの伝えた“よきたより”
第3巻 ルカの伝えた“よきたより”
第4巻 ヨハネの伝えた“よきたより”
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
梟をめぐる読書
シナモン
Koning
marumichan
Sosseki
-
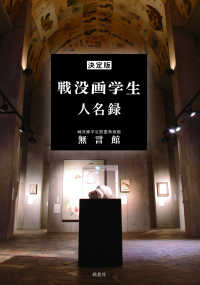
- 和書
- 決定版戦没画学生人名録