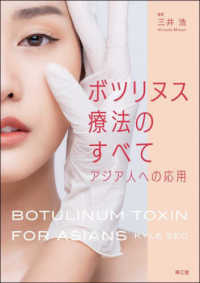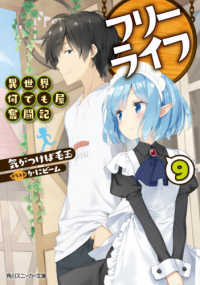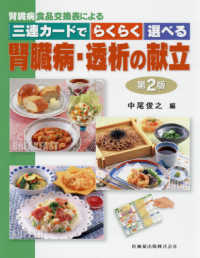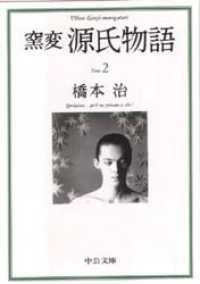出版社内容情報
「無信仰の信仰」を背景とする、現代日本人の揺れ動く死生観の構造を4つの視点で解析。
それと対比させ、個人の死を初めて真正面から取り上げた、親鸞・道元ら中世新仏教の宗祖たちの、現世を越える死生観を論じる。
Ⅰ現代日本人の宗教意識
日本は宗教の博物館/多重信仰の実態/天皇と神道、仏教と葬式/なぜ「無信仰の信仰」か
Ⅱ現代人の死の見方
臨死体験/脳死臓器移植をどう考えるか/キューブラーロスと葉っぱのフレディ
Ⅲ中世仏教の死生観
なぜ中世か/地獄と極楽/鎌倉新仏教の思想空間/宗祖たちの死生観
ほか
仏教が「無信仰」の信仰と化したのは、近世から近代にかけての政治とのからみによるものであり、その点、すぐれて歴史的な所産と言わなければならない。したがって現代の私たちが生と死あるい来世観を含めた総体としての仏教を学ぶとすれば、それは「無信仰の信仰」以前の古代・中世の仏教をおいて他にはない。・・・・・・・・(本文より)
内容説明
「無信仰の信仰」を背景とする、現代日本人の揺れ動く死生観の構造を4つのベクトルで解析し、それと対比させて個人の死を初めて真正面から取り上げた中世新仏教の宗祖たちの、現世を超える死生観を論じる。
目次
第1部 現代日本人の宗教意識(日本は宗教の博物館;多重信仰の実態;天皇と神道、仏教と葬式 ほか)
第2部 現代人の死の見方(臨死体験;新しい死;脳死・臓器移植をどう考えるか ほか)
第3部 中世新仏教の死生観(なぜ中世か;地獄と極楽;鎌倉新仏教の思想空間 ほか)
著者等紹介
佐々木馨[ササキカオル]
1946年、秋田県生まれ。1975年、北海道大学大学院文学研究科博士課程中退。専攻、日本中世仏教史。現在、北海道教育大学教授・北海道教育大学附属函館小学校長(併任)。文学博士
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 日本中世思想の基調