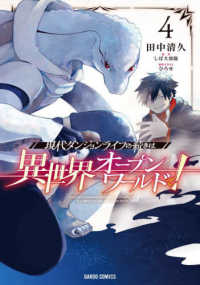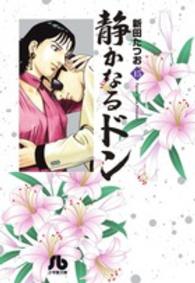出版社内容情報
学校現場の危機、学力低下・学級崩壊を救うのは、学力と人格を真にきたえ、一人ひとりをいきいきとさせる技術=一斉授業だ!
一斉授業は、これまで、画一的な詰め込み教育の象徴と思われてきたが、個と集団の学びあいが両立できるところにその本質がある、と著者は説く。一斉授業の驚くべき〈教育力〉をわかりやすく示す、理論と実践の書。
第1章 いまなぜ一斉授業なのか
1 「均質で広範な学力」をつける/2 憲法と教育基本法に則った教育とは/3 一斉授業の意味と価値/4 個と集団、「教え」と「学び」/5 授業で学力と人格を育てる
第2章 学力のつけ方──一斉授業の実践的意義
1 すべての学習能力を鍛える一斉授業/2 どの教科でも音読をする/3 学力の要=読解力を育てる/4 文字指導──長期的な展望をもって取り組む/5 ノート指導で教育する/6 計算力をどうつけるのか/7 「算術から算数へ」と進む/8 言葉を征するものは授業を制する
第3章 「新しい学力観」の嘘と幻想
1 「新しい学力観」のもたらしたもの/2 学力的自立という観点から/3 「個性尊重」という名の教育放棄/4 「指導でなく支援」の誤り/5 「子どもの興味から授業を」という呪縛
日本の教育は世界に誇る二つの宝をもっています。一つは江戸時代、寺子屋でつくりあげられた「読み・書き・計算」の技であり、もう一つは学制発布以来、日本の教師が百年間、営々と築き、伝え合ってきた一斉授業の技です。(中略)
個としての学びを位置づけながら、集団として学び合う──それを可能にするのが一斉授業です。日本人の「小さな英雄」としての力は、この一斉授業による教育の所産です。教師と子ども集団が対峙し、〈々しい個別化〉がなされ、個別化された一人ひとりが〈ゆたかな交流〉をすることで、これが実現されてきたのです。
ところが、いまその一斉授業を行なう教師の技が失われようとしています。(中略)
私は、現在の教育の混乱は教育基本法や憲法の精神からの逸脱によって生じたものだと考えています。
目の前の問題に振りまわされ、あるいは耳あたりのいいスローガンに惑わされて、この基本精神を忘れていないでしょうか。どの子にも学力をつけ、そのなかで人格の完成をめざすという基本を取り戻したときに、一斉授業の必要性と重要性が見えてくるはずです。
もう一度、日本の教育の誇る二つの宝に着目し、教師自らの一斉授業の技を高めることに力を注いでみませんか。
学力低下、学級崩壊を救うのは一斉授業だ!「新しい学力観」「個性尊重」「指導でなく支援」「子どもの興味から授業を」など、近年の教育改革のキーワードが引き起こす事態の誤りと過ちを批判しながら、一斉授業の実践的意義を展開する。発問・板書・ノート指導など一斉授業の中核をなす技をもう一度取り戻し、磨いていくことが教師にとって大切です。〈凛々しい授業〉でどの子にも平等な学びの保障を!
内容説明
学力低下・学級崩壊を救うのは一斉授業だ!学力を真に鍛え、子ども一人ひとりをいきいきさせる、その驚くべき“教育力”を示す理論と実践の書。
目次
第1章 いまなぜ一斉授業なのか(「均質で広範な学力」をつける;憲法と教育基本法に則った教育とは;一斉授業の意味と価値 ほか)
第2章 学力のつけ方―一斉授業の実践的意義(すべての学習能力を鍛える一斉授業;どの教科でも音読をする;学力の要=読解力を育てる ほか)
第3章 「新しい学力観」の嘘と幻想(「新しい学力観」のもたらしたもの;学力的自立という観点から;「個性尊重」という名の教育放棄 ほか)
著者等紹介
久保斎[クボイツキ]
1949年京都市生まれ。京都教育大学教育学部哲学専攻卒業。京都市の公立小学校教師。「学力の基礎をきたえどの子も伸ばす研究会」常任委員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。