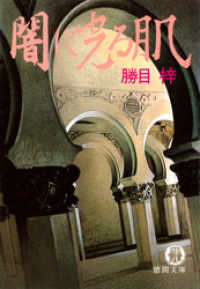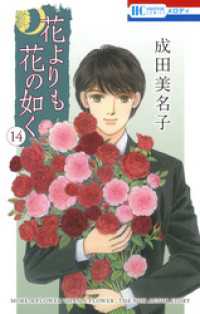内容説明
佐賀鍋島藩祖直茂、初代勝茂は、戦国の余燼くすぶる時代を生き、仕える家臣たちも、主君の馬前で討死して武士道の全うを願った。しかし、時代は大きく変わる。二代光茂は武断な家風を厭い、追腹(殉死)を禁止。自らは命を懸けて和歌を極め、古今伝授の秘伝を受け、超一流の文化人となる。光茂が没するまで懸命に仕えた『葉隠』の語り手・山本常朝は、命を懸けた覚悟ある生き様こそ、人の命が輝くことを伝えたかった。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
優希
38
『葉隠』をベースにした歴史小説でした。『葉隠』は読んでいなかったのですが、それでも佐賀藩に残した影響の大きさなどが掴めます。『葉隠』はいつか読んでみたいですね。2023/12/19
アッキ@道央民
30
久々に読んだ歴史小説。今年直木賞を受賞した著者の作品を読んでみたいと思い図書館で借りて来ました。 佐賀鍋島藩の創成期。武断政治から文治政治に変わりつつある時代にあって、主君のために命をかけて忠誠心を捧げる家臣達の想いには頭が下がります。葉隠の語り手山本常朝の真っ直ぐなまでの生き方は男としても魅力を感じました。2013/07/08
detu
23
1/13〜16了。図書館より。「武士道は死ぬことと見つけたり」で有名な『葉隠』そのものを読んでいないが、これを読んで佐賀鍋島家の成り立ち、佐賀藩の歴史、気風、風土がよく分かり伝わる。近頃ハマり安部龍太郎。これも拾い物だった。2023/01/16
ともくん
16
鍋島武士の教科書。 鍋島武士の矜持だ。 山本常朝『葉隠』を娯楽性に富み、且つ、分かりやすく、当時の武士道とは何か描いた。 武士道とは―死ぬことと見付けたり。2018/05/13
ピンクピンクピンク
10
『葉隠』は鍋島藩氏山本常朝が口述した初代藩主直茂から三代光茂までの間の鍋島武士、曲者達の昔語を筆録しまとめたもの。本書は二十三話からなる物語の頭に『葉隠』からの一節が引用され展開される構成。語られる「武士道」が潔く、義に暑くて格好良い。信義に心血を注いで生きた登場人物の様が実に爽快です。2017/06/14