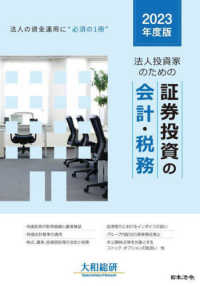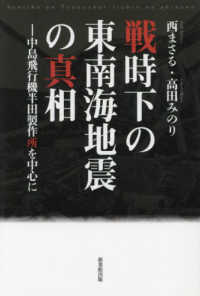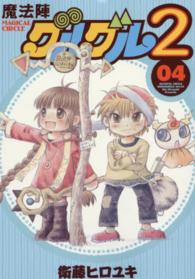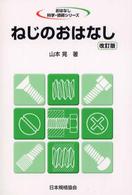- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 哲学・思想
- > 日本の哲学・思想(近世)
内容説明
歴史からこぼれおちた国学の精神が、こんなにも日本の文化・精神風土に息づいているとはだれが考えただろうか。江戸時代の愛国思想に学ぶ「美しい国」のあり方。
目次
第1章 「国学」入門
第2章 国語の成り立ち
第3章 国学者が夢見た「日本」の姿
第4章 対立する宗教と霊界のはなし
第5章 日本文化へのまなざし
第6章 現代社会に生きる国学思想
著者等紹介
中澤伸弘[ナカザワノブヒロ]
昭和37年東京生れ。國學院大学文学部文学科卒業後、都立高校国語科教諭。現在、都立足立高校教諭。専攻分野は国語教育をはじめ日本文化史、国学史、国学思想史、近世後期和歌史。それに関する古書籍の蒐集など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
syota
22
①江戸時代に成立してから第二次大戦に至るまでの国学の流れが、1項目2ページでわかりやすく述べられている。私のような素人が国学を理解するには最適の一冊。公文書は漢文(中国語)、国を動かす思想は儒教に仏教という長年の状況に疑問を感じ、日本古来の言葉や文化を探ろうとした国学誕生の動機には十分説得力がある。契沖、賀茂真淵、本居宣長といった先人の業績には心から敬意を表したい。少なくとも宣長までの国学は客観的な文献研究が主であり、「学」の名にふさわしい内容だったと思う。(続く) 2018/10/11
左手爆弾
3
高校の国語をメインにしている先生が書いた本なので、大変わかりやすい。一つのテーマに深入りしすぎることなく、それでいて核となるところは伝えてくれている。古典に忠実な真淵や宣長に対して、国学を意欲的に展開しようとする平田篤胤との対比が興味深い。国学者は基本的に幕藩体制の中で生きた人々だったので、天皇を中心とする体制には関心がなかった。彼らはあくまでも古の日本語や、日本の精神性に興味があっただけ、というのが著者の主張。そこは納得できるが、「自虐史観」という言葉を使っているのは気になった。2021/09/13
xin
3
国学についてその基本知識と興味深いトピックごとにまとめた本。「やさし」い割りには結構読みがいがある。2014/03/02
lalaright
3
恥ずかしながら「国学」という学問を初めて知った。この国を形成する学問にこれほどまでに悪戦苦闘して学び続けた人たちがいたのかと感動を覚えた。明治維新後の国学者たちの「夜明け前」の絶望は想像して余りある。しかし、それでも屈せず、学び続ける姿勢に、勇気を与えられた。これは図書館で借りた本だが、amazonで買い直した。一生読み続け、私も学び続けたいと思う。2011/01/30
フルボッコス代官
1
国学と言えば、愛国思想・保守思想の原点みたいなとぼけたこと言う人がいるが、和歌・仮名遣い・外国学問の日本化など多くの面で貢献しているのが国学。日本文化の成り立ちを平易に解説しているので、定義づけとまではいかないが、国学とはなんぞやと知るのには最適。2020/08/21
-
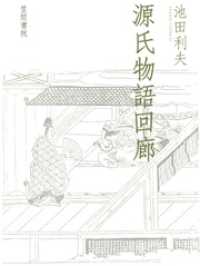
- 電子書籍
- 源氏物語回廊