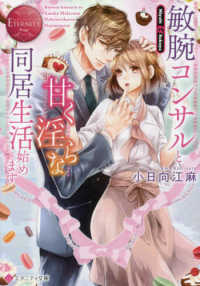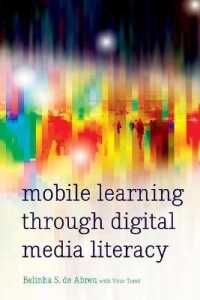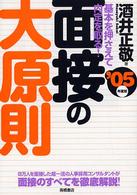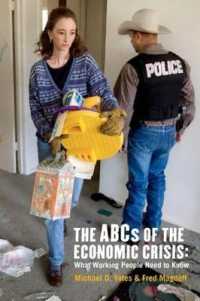内容説明
都市を創造してきた巨匠たちの至言。いかなる思想で世界のカタチをつくってきたのか。そしてそのあるべき姿とは何か。建築のマエストロたちが「新世紀の都市」を語った、画期的連続講座の記録。
目次
はじめに―都市の証言
概説・都市を俯瞰する地球学の眼
離散都市に向けて
連続講座1 離散都市、もしくは浮遊する集落
風景の構築
連続講座2 都市―夢と記憶の場所
共生の都市
連続講座3 生命の原理、共生の思想
著者等紹介
石井和紘[イシイカズヒロ]
1975年東京大学大学院工学系研究科建築学専攻博士課程修了。76年石井和紘建築研究所を設立。カリフォルニア大学ロサンゼルス校、イェール大学、東京大学などで教鞭をとる。東京大学大学院在学中の24歳の時、直島町立小学校を設計、以来島の幼稚園、体育館、中学校、町役場などを次々と手がける。主な作品に「54の窓」「JAZZYなバロック」「同世代の橋」「ジャイロ・ルーフ」「数寄屋邑」などがある
原広司[ハラヒロシ]
1964年東京大学大学院数物系研究科建築学専攻博士課程修了。東洋大学助教授を経て、69年東京大学生産技術研究所助教授となり、のち教授に就任。97年東京大学を退官、名誉教授となる。設計活動は70年以降アトリエ・ファイ建築研究所と共同。1970年代に“反射性住居”として知られる一連の住宅を設計。89年から「新梅田シティ開発計画」に携わる。主な作品に「田崎美術館」「ヤマトインターナショナル」「連結超高層‐新梅田シティ」「内子町立大瀬中学校」「JR京都駅」などがある
槇文彦[マキフミヒコ]
1954年ハーバード大学大学院建築設計専攻修士課程修了。56年ワシントン大学準教授、62年ハーバード大学準教授、79年~89年、東京大学教授。65年に槇総合計画事務所を設立。モダニズムの思想を受け継ぎ、洗練された建築空間を創り出す。奥庭や路地など、日本的空間を織り込んだ作品でも知られる。主な作品に「名古屋大学豊田講堂」「代官山ヒルサイドテラス」「藤沢市秋葉台文化体育館」「スパイラル」「幕張メッセ」などがある
黒川紀章[クロカワキショウ]
1964年東京大学大学院建築学科専攻博士課程修了。62年建築都市設計事務所を開設。98年より日本芸術院会員。26歳でメタボリズムグループを結成。機械の時代から生命の時代への変革を提唱し、海外ではドイツ、フランス、アメリカ、イタリア、オーストラリア、中国等世界20ヶ国に及んで活動。98年よりカザフスタンの新首都アスタナの建設を担当。主な作品に「国立民族学博物館」「国立文楽劇場」「広島市現代美術館」「奈良市写真美術館」「ヴァン・ゴッホ美術館新館」などがある
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-

- 和書
- 怒りのロードショー