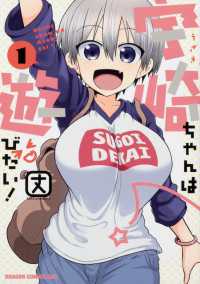目次
茶の心(日本的ということ;なぜ日本で茶が栄えたか;茶の精神―禅とのつながり;堺の興亡 ほか)
つれづれなるままに(身をもって体得せよ;小さな抵抗;老いもまた楽しからずや;風流ということ ほか)
著者等紹介
立花大亀[タチバナダイキ]
1899年、大阪堺市生まれ。1921年、堺市南宗寺にて得度。1931年、大徳寺塔頭徳禅寺住職。1953年より大徳寺宗務総長、のち顧問、管長代務。1968年、大徳寺511世住持となる。以後、大徳寺最高顧問。1972年、大徳寺山内に如意庵再興。1979年、奈良大宇陀に松源院再建。1982年より花園大学学長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
B.J.
13
<切腹>利休切腹の真相は、この中に! 2014/07/14
Y
2
利休の切腹にはいろいろな云われがあるけれど、三成の陰謀というのは一番しっくりときました。2016/02/29
Nami Tsubokura
0
前半が茶道や利休の話。後半が今置かれている世界のことや禅の世界のお話しや人間の業などに触れています。日本でかな文字が生まれたように、中国から来た茶が柔らかいものになっていく様子。路地の意味や玄関は幽玄への関門だという話。無いものを見せる文化。私はお茶の世界は悲しいことに不勉強ですが、特に前半はとても興味深く読みました。2013/05/11
RINA
0
読了。2013/01/23