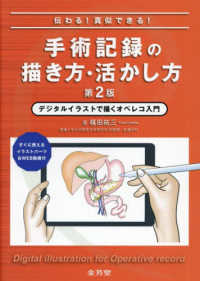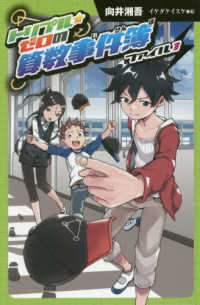内容説明
伝承に生きる糸、かつては全国で栽培されていたカラムシ。中国・フィリピン・マレー半島が原産地であったカラムシはいつ頃、どのような伝播ルートをたどって日本にきたのだろうか。昭和村をはじめとして、カラムシの伝統を知る。
目次
第1部 会津のカラムシ
第2部 最上・米沢地方のカラムシ
第3部 小千谷縮と昭和村の邑伝織りについて
第4部 カラムシの伝播ルートを求めて
第5部 沖縄地方のカラムシ
第6部 台湾のカラムシ
第8部 カラムシの里は今
著者等紹介
滝沢洋之[タキザワヒロユキ]
1940年大沼郡金山町に生まれる。1963年福島大学学芸学部卒業。福島県立高校教員を勤める。現在、会津民俗研究会会長、青木山を守る会会長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
バーニーズマウンテンドッグ
0
カラムシはイラクサ科の植物でかつてその繊維から衣類を作った。日本中そして中国や台湾、朝鮮半島でこの織物の文化があった。それなのに、今、日本で残っているのは、会津地方の昭和村、山形県、沖縄などごくわずかである。小千谷縮の原料がこのカラムシで、昭和村で生産された糸が六十里越の峠道を運ばれた。良い糸をとるためにカラムシに風除けをして育て、刈り取ったカラムシを水につけ、爪で繊維を取り出して、依って糸として、地機で織る・・・ほとんど失われかけた文化が村の人の努力で30年以上かけて戻ってきたそうである。2016/12/15