内容説明
コロンブスが持ち帰ってから、わずか500年余りで世界中に広まった不思議な食べ物トウガラシ。各地の食文化と結びついて新たな味をはぐくみ、人びとを虜にしてきたその魅力を、食文化論から辛みの科学まで、さまざまな角度から紹介。世界各国のトウガラシ料理の簡単レシピ付き。
目次
トウガラシ誕生の地―中南米
胡椒を求めてトウガラシを得る―ヨーロッパ
シンプルに、より複雑に―アフリカとアラブ
エスニックをさらに豊かに―東南・南アジア
伝統料理との幸せな融合―東アジア
結び トウガラシ、その魅力の秘密
著者等紹介
山本紀夫[ヤマモトノリオ]
1943年生まれ。京都大学大学院博士課程修了、農学博士。現在、国立民族学博物館名誉教授、総合研究大学院大学名誉教授。専門は民族学、民族植物学、山岳人類学。1968年よりアンデス、アマゾン、ヒマラヤ、チベット、アフリカ高地などで主として先住民による環境利用の調査研究に従事。1984~87年には国際ポテトセンター客員研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
leo
12
前に同じ著者のトウガラシ本を借りて、微妙だったの忘れてまた借りてしまった…けど、本著は地域ごとに違う研究者が執筆しているので飽きずに読めた。トウガラシの伝播の仕方よりも、より料理法や文化史に寄ってたのもよかった。しかし誤字が多い…3箇所ぐらいみつけた…2020/08/25
ピオリーヌ
11
トウガラシについて、原産地である中南米からヨーロッパ、アフリカとアラブ、東南・南アジア、東アジアと世界を一周しながら、現地の様々なトウガラシ料理を紹介する内容。コロンブスはヨーロッパへトウガラシを持ち帰ったが、気候の違いによる栽培の困難さ、比類のない辛みにより容易に受け入れられなかった。今なおドイツやイギリスなどヨーロッパ北部の地域ではトウガラシがあまり使われていない。そのヨーロッパでも冷涼地で育つ辛みの少ない品種が栽培されるようになっていった。ハンガリーが代表的である。トウガラシの一品種のパプリカが2024/02/15
いとう・しんご
10
読友さんきっかけ。「哲」分補給の後は薬味を追加です。新世界から出発して東アジアまで、世界中のトウガラシ料理を巡る旅に連れて行ってくれる本で、思わず唾が沸いてきて辛いものが食べたくなりました。最後にカプサイシンの健康増進効果についての最新の医学研究のお話が出てくるところもなかなか心憎い構成だな、と思いました。2024/03/29
Yoshiki Ehara
2
南米原産で、大航海時代に世界中に広がり、今ではどこの料理でも欠かせなくなっているトウガラシ。本書では中南米、ヨーロッパ、アラブ、アフリカ、南アジア、東南アジア、そして我らが東アジアまで、各地域自慢のトウガラシ料理と文化をこれでもか、というくらい紹介される。しかも、執筆者は各地域の文化に精通した民俗学や農学などの専門家たち。全てのページ、写真からトウガラシへの偏愛が滲み出ていて、読むほどに口の中がヒリヒリしてくる(ような気がする)。辛いのが好きな方には、ぜひ挑戦して欲しい一冊です。2014/09/08
夏みかん
1
先に読んだ新書のトウガラシの本よりも内容が濃くて満足。特に、世界各地の色々な種類のトウガラシやそれを使った料理の記述が多いのが良かった。 2019/08/20
-

- 電子書籍
- 私たちはどうかしている 妻恋い 分冊版…
-
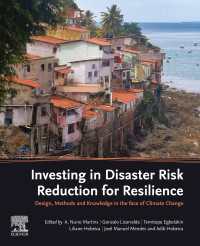
- 洋書電子書籍
- レジリエンスのための防災リスク縮減への…
-

- 電子書籍
- 日経トレンディ 2014年 05月号
-
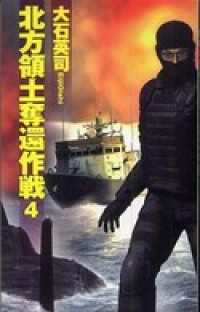
- 電子書籍
- 北方領土奪還作戦4 C★NOVELS





