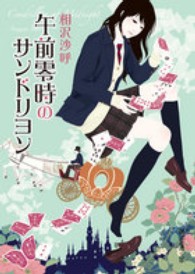内容説明
我国の考古学は、現在でも「発展段階論」に立脚した研究が主流である。定説によれば、貧しい縄文人は、大陸・半島から水田稲作を携えてきた弥生人に救われたことになっている。しかし、最近発表されたAMS(加速器質量分析法)の研究により、弥生時代の開始年代が定説より五〇〇年溯る可能性が出てきた。ここから、弥生の水田稲作の急激な広がりは否定され、階級社会の成立も急速ではなかったことが分かる。著者は、「もの」を軽視したイデオロギー優先の通説・定説を批判し、遺跡・遺物から十分に古代日本列島の歴史像・国家発生のメカニズムを説くことが可能であると主張する。
目次
第1部 日本考古学“再考”(日本考古学の“存立基盤”を問う;新しい弥生開始年代説の衝撃)
第2部 考古学の通説・定説を疑う(“貧しい縄文”を弥生文化が救ったのか;コメの余剰生産が支配層を生み出したのか;弥生時代に都市は存在した;前方後円墳とはなにか;“カミ”や“他界”を考古学は論証できるのか)
著者等紹介
広瀬和雄[ヒロセカズオ]
1947年京都市生まれ。大阪府教育委員会、大阪府立弥生文化博物館などを経て、現在、奈良女子大学大学院人間文化研究科教授。同志社大学卒業。日本考古学専攻
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
perLod(ピリオド)🇷🇺🇨🇳🇮🇷🇵🇸🇾🇪🇱🇧🇨🇺
5
再読。『万物の黎明』を読んで再読したくなった。2003年の本で対象は弥生時代ながら参考にはなるはず。 日本考古学には実証もされていないにもかかわらずたいした批判もなく通用して既定の事実であるかのような説があり、それを通説と呼んでいる。本書では主にマルクス主義史観が批判されている。人類の歴史は階級闘争の歴史であるとか、未開→野蛮→文明という発達史観だとか、実証置いてけぼりの理論先行頭でっかちな学者センセイはそれへの反証的な発見があっても「それはおかしい」とのたまう。→2024/04/17
perLod(ピリオド)🇷🇺🇨🇳🇮🇷🇵🇸🇾🇪🇱🇧🇨🇺
4
2003年刊。第一章:日本の歴史学は戦前は皇国史観、戦後はマルクス主義的唯物史観の影響を受けていて、現実の歴史との乖離が甚だしい。そこから離れて新たな歴史を考古学の面から進めて行く。また、いわゆる通説・定説が実証されることなく通用していると指摘し、そこも含めて検証されなければいけない。 第二章:弥生時代の開始が500年遡るという最新の研究成果と、それを疑問視する通説側と。訂正されるべきは通説。→続く 2021/02/24
a43
3
縄文時代が全くスッパリなくなって弥生ではないのは知っていたが、沖縄には貝塚なんとか文化というのがあった!!知らなかった!2014/07/14
おらひらお
3
2003年初版。著者の指摘の通り、通説を前提として論を組み立っている論文も多くみられますが、最近の概説書ではそこに突っ込むものもみられるようになってきています。著者の弥生都市論も再評価されていましたし・・・。2012/12/07
綱渡鳥
1
出版は2003年とすでにひと昔前の著作だが、ここで提示された課題はまだ解決されていない。考古学、というか歴史学全体に「発展段階論」は根強くはびこり、中々払拭できない。加えて、考古学の学問上の課題ではあるが、新たに資料が増え続けるため、個別形態論的研究に多くの研究者が膨大なエネルギーを投じていると説く。それは大事なことだと留保しつつも、そこにとどまっていては歴史の復元という最終目標には近づいていかないというのが著者の主張。ではどうすればいいのか、それは本書を最後まで読んで欲しい。2019/04/13