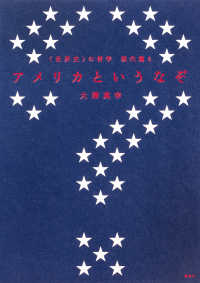内容説明
日本語圏のネットにおいて二一世紀初頭は大きな節目にあたる。二〇〇三年から始まる高校の「情報科」は、その有力な分岐点になるが、構想されているその内容は、およそ「インターネット的」なるものが排除された古めかしい情報工学教育の域を出ない。いま切実に求められているのは、インターネットの驚異的な展開によって再編されつつあるネットワーク社会を生きぬくための知識と知恵、すなわちインフォアーツなのだ。新しい躍動的なネット社会への扉を開くために発せられた問題提起の書。
目次
第1章 大公開時代―自我とネットと市民主義
第2章 メビウスの裏目―彩なすネットの言説世界
第3章 情報教育をほどく―インフォテックの包囲網
第4章 ネットワーカー的知性としてのインフォアーツ
第5章 着地の戦略―苗床集団における情報主体の構築
第6章 つながる分散的知性―ラッダイト主義を超えて
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
茶幸才斎
4
インターネット普及初期にあった市民主義的言説空間は、先行文化を知らないユーザーの大量参入により数年で消え去り、流言と極論が幅を利かせる否定的側面が常態となった。故にこそ情報教育が重要なのだが、それは単なる情報処理に関する技術的知識(インフォテック)ではなく、ネット社会の主体として良好に振る舞える知識と知恵(インフォアーツ)であるべき、と論じている2003年出版の本。2020年の小学校プログラミング教育必修化を総務省と経産省が後押しするなど、いまだ国が目指す情報教育とは、IT産業振興策の色合いが濃いようだ。2017/05/27
takachan
0
そんなに深刻に考えることだろうか?と今となっては思ってしまう。2010/03/27
たぬき
0
2003年の書籍、揚げ足を取るには突っ込み所が満載だが、方向は出せても、実態がおぼろげに2009/07/12