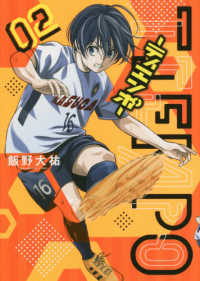内容説明
一九五九年の伊勢湾台風で、愛知県内の旧家の崩れた土蔵から発見された「前野文書」は、のちに『武功夜話』と題して公刊された。同書はNHKや朝日新聞などのメディアが、戦国時代を解明する第一級の史料として喧伝したり、遠藤周作や津本陽らの有名作家の作品に種本として使われたことから、その内容が史実として一人歩きすることになる。しかし、同書はその原本が公開されていないために、用語や記述に多くの疑問がありながら、専門家の検証すらなされてこなかった。在野の戦国史研究の第一人者が、様々な角度から徹底検証し、真贋に決着をつける。
目次
序 戦国文書『武功夜話』とはどんな史料なのか?
偽書研究(1) 「武功夜話」はどのようにして作られたのか?
偽書研究(2) 一級史料『信長公記』と偽書『武功夜話』を比較する
偽書研究(3) 捏造された秀吉の出世譚「墨俣一夜城」
偽書研究(4) 偽書を喧伝したマスコミ、有名作家、研究者の責任
偽書研究(5) 『武功夜話』がねじ曲げた戦国合戦史
著者等紹介
藤本正行[フジモトマサユキ]
1948年東京都生まれ。慶応義塾大学文学部史学科卒業。現在、株式会社彩陽代表取締役。日本軍事史・風俗史専攻。軍事・絵画・城郭・甲胄武具研究を有機的に集合した独自の歴史研究を展開している
鈴木真哉[スズキマサヤ]
1936年横浜市生まれ。中央大学法学部法律学科卒業。防衛庁、神奈川県等に勤務。在職中から、「歴史常識」を問い直す研究を続ける
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゲオルギオ・ハーン
22
一時期は太田牛一の『信長公記』に並ぶ一級史料ともされ、小説の元ネタに使われたり、戦国時代の新事実が書かれているともてはやされた『武功夜話』について内容の検証をした一冊。要点は最初の三分の一くらいで書かれており、「墨俣一夜城」や「山崎の戦い」などの記述の細部についての指摘は少ししつこい印象があった。個人的には偽書を調べる面白さは数多ある偽書の中でその本がクローズアップされた背景やそれを利用して観光名所や小説のネタにされていく背景の分析だと思うのでその点も踏み込んで欲しかった。2024/06/22
邑尾端子
6
現代になって突然登場した日本中世史上のアイドル的偽書『武功夜話』について、その偽書たる論拠の解説と、この偽書が世間にもて囃され広まってしまった経緯等を紹介する一冊。武功夜話が偽書である根拠の証明は、主に一級資料『信長公記』との内容の比較に依っていて、それに関しては若干『信長公記』を過信しすぎているきらいはあるものの、『武功夜話』が明治以降の価値観のもとに書かれた創作味の強い文書であるかということはよく理解できた。実際の成立年代に関する考察が面白い。2017/08/20
May
5
(記録として昔の文章を。読了日不明)伊勢湾台風で被災した旧家の土蔵から出てきた古文書を編纂したものとされる「武功夜話」と総称される文書が偽書であることを論じたもの (元の古文書は通常「前野文書」と言われている)。両氏とも様々な角度から偽書であることを論証しているが、その論拠の主なものは以下のとおりである。1.戦国期らしくない文体、用語、表現が散見する(ヒソヒソ話なんてものもあるようで、笑ってしまった)2.戦国期の常識を知らない人が書いている(価値観、暦の誤り、風俗等) 2008/10/01
鐵太郎
4
「武功夜話」とは、単にあとで書かれた自分に都合のいいフィクションでしょ? と言うのがこの本の要旨。そこまではよし。しかし、それもまた一つの見解であるのだから、巻末の「初版第2冊あとがき」のような、─我々の見解に対し文句があるのなら、論拠を出した我々の前に提示して反論しなさい─ 的な物言いは、いかがなものか。と思いますよ。一つの価値観で決めちゃあ、歴史のような曖昧な世界は面白くないと思うな。技術の世界ですら、時と場合によって2プラス2が4にならないときがある。まして、人と人が築き上げた歴史に於いて、ね。2008/11/28
hyena_no_papa
3
ここの感想で見かけたので読む。感じたことは三つ。かの『東日流誌』のケースと同じ匂いがしたこと。著名な作家やNHK、出版社まで担がれた?こと。『東日流誌』とほぼ同時期であること。匂いについてはそっくり。原本が出ない、貸し出し無用、書式が合わない、閏月を知らない、年齢が合わない、戦後の地名が出てくる、一部に早い時期から偽書と看破していた人がetc.違うのは偽作者の顔が見えないこと。小和田哲男氏の批判と対する反論のその後は?双方の議論を読まねば断定できないが、『東日流誌』の追っかけをやった人間からするとクロ!2020/02/15