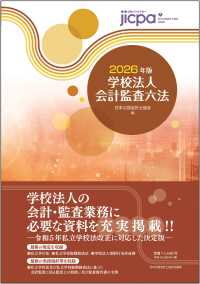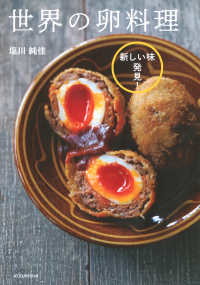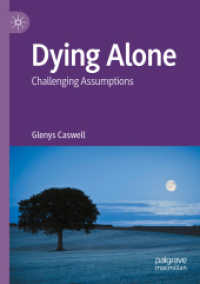内容説明
新聞「時事新報」に掲載された、職人言葉、悪態、減らず口、落語もどきを一席のこともあれば、ほめ殺しや大ホラもあたりまえ、縦横無尽やりたい放題の中に真実を語り込むコラム「漫言」を追い、明らかにする文明開化の実像。
目次
プロローグ 楠公権助論
第1章 “漫言”登場
第2章 ホラを福沢 ウソをいふ吉―漢儒者攻撃
第3章 “漫言”に見る明治―帝国議会開設前後まで
第4章 民権論と官民の衝突
エピローグ 大日本帝国憲法発布
著者等紹介
遠藤利國[エンドウトシクニ]
1950年生まれ。早稲田大学大学院博士課程修了。翻訳家、國學院大學講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
扉のこちら側
33
初読。福沢諭吉の「ハデにバカいう」やりたい放題だったコラム「漫言」について。語彙が貧困でうまい表現が見つからないのだが、やんちゃな福沢諭吉が楽しめる。2013/09/16
きいち
26
福沢諭吉、若い時分に「学問のすすめ」をななめ読みして以来、その「正しさ」があまり好きになれず、でも『陽だまりの樹』の、適塾で手塚良庵にからむ闊達さは印象が違ってて、それがずっと気になっていた。この本はまさにそのミッシングリンクを埋めてくれる一冊、力強くてやんちゃな戦略家としての福沢が味わえる。考えてみたら「学問の~」だって才走った若書きの一冊、それをお札の福沢のまま読んだらいかんわな。◇この本は明治憲法まで。続編も続けて読みたいけど、その前に『福翁自伝』に行くかな。手塚とのエピソードは自伝からだというし。2014/10/26
壱萬参仟縁
6
漫言とは、「冗談とか放言に類する論」(61ページ)という。「福沢の生涯は、喧嘩、また喧嘩の連続で、けっしてひるむことがなかった」(149ページ)とは心強いし、共感できる。「貧しい社会にあっては、平等ではないからこそ不満を解消させるための巧妙な抜け道も用意」(183ページ)できたようだから、なるほど、今日の格差社会は学ぶ時代ではないか。時折出てくる宮武外骨の挿絵が効果的な時代描写があるので、好感が持てる。
こと
3
なーるほど、という感じ(笑)。福沢って、こういう人かなとは思っていましたが、ここまでふっきれた文を書いていたのは知りませんでした。頭良すぎ。2014/05/31
はらぺこ侍
2
欧州にて忠の世界ではない数の世界を見た福沢諭吉。今まで研究者間であまり着目されなかったように思う時事新報コラムから彼の人となりを知るのはとても楽しい。
-

- 電子書籍
- 恋愛弱者の美貌録7 素敵なロマンス