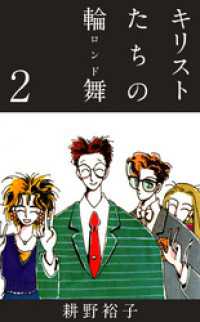内容説明
米・オハイオ州とペンシルバニア州を中心に文明の利器を使わず、皆が助け合って生きる、シンプルでありながら心豊かな暮らしぶりのキリスト教再洗礼派の共同体「アーミッシュ」。その暮し振りと底に流れる思想を丁寧に紹介。ストレス社会に生きる我々の癒しともなる書。
目次
アーミッシュとはどのような人たちか
アーミッシュの歴史
穏やかに、心豊かに生きる―ゲラッセンハイト‐生き方の基盤となるもの
手作り中心のエコ生活
仲間との絆―互いに助け合い、心豊かに生きる
アーミッシュの学校教育―なぜアーミッシュの子どもたちは全米学力テストで上位成績を収めるのか
アーミッシュの子育て―働くことで多くを学ぶ子どもたち
アーミッシュの若者たち
アーミッシュの赦しとそれを育むもの―西ニッケルマインズ校襲撃事件を通して
よりよい社会を次の世代に―アーミッシュ社会の規律オルドゥヌング
結婚
年をとっても、体が不自由になっても
死
著者等紹介
堤純子[ツツミジュンコ]
1957年生まれ。学習院大学文学部英米文学科卒業後、15年以上翻訳の仕事に携わる。その後現在まで、小学校英語講師、小論文添削指導、及び塾講師として、小中高校生の学習指導にあたっている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
袖崎いたる
4
アーミッシュについて。彼らの生きかた感じかた考えかたが気になっていたので、手にとる。ドイツからの移民なんだね。犠牲精神を持っていて、聖書本意の生きかたをしている。文明になるべく染まらないようにしている彼らの生きかたは、とはいえ文明の坩堝に間借りするかたちで営まれるわけで、借りぐらし意識はたえず付き纏っているみたい。この点に半グレや不良たちの姿を重ねてしまう。アーミッシュ自体は博愛ではあるがね。身内が殺されても神の思し召しととらえる様子は崇高、ある種不気味な気配がありつつ、独自の存在感を放っているのは確か。2024/12/24
ヨハネス
3
新聞の書籍広告が目にとまり読んでみました。アーミッシュって初耳。軍隊?先住民族?どちらでもありませんでした。聖書の教えを守るため、17世紀のドイツやスイスの暮らしをアメリカに移住してまで続ける人々。電気もガスも原則使わない生活はアズマカナコさんと似ています。アズマさんは周囲から浮いてしまうだろうけど、アーミッシュは右肩上がりに人口増加しアーミッシュだけの集団があるから暮らしやすいだろうな。地球を傷つけない暮らしは人間にも実は理想的なんだと思います。日本なら、江戸時代の暮らし。ご近所、親戚と助け合う暮らし。2013/11/18
Saiid al-Halawi
3
馬車、黒服と山高帽、自給自足の零細農業と工芸、的な牧歌的イメージが強いアーミッシュだけど、教区によっては非アーミッシュの運営する電車やタクシーを使うようなところもあるんだと。それと私たちの世界でいうと大学時代くらいに相当する何年かのモラトリアムが若者に用意されてて、その期間にサークルのようなグループに所属して、俗世間に触れて非アーミッシュの世界を知るんだと。それと生きた言語としての古ドイツ語には惹かれるなー2012/03/12
バーベナ
2
納屋が消失しても、すぐに生活に必要なものだから、1週間で建ててしまったり、保険制度や学校も独自の運営をしている。アメリカに住まわせてもらっているのだから納税はする、しかし自治を守るため援助は受けない。その結束の固さの裏には、迫害の歴史が身体に沁み込んでいる。一部分だけをみて、あれこれ言うことは控えたいけれど、結婚式でのアーミッシュの敬虔な祝い方は本当に素敵だと思った。ひとりになりたいときはないのだろうか、と思ったけれど、そんな暇もないほど忙しい毎日。2021/05/18
おばこ
2
難しいかと思ったが、読みやすい本でした。 この百年ほどでアーミッシュ人口は右肩上がりに増加(彼らも集団が先細りにならないよう沢山子供を産み育てる)。アーミッシュもグループによって ストイック派からおおらか派まで様々。 単なるスローライフとは違い、宗教であるから、制約も多く、私には息苦しさも感じられた。助け合いの精神は素晴らしい。日本もその昔はこういう社会だったのだろうけど。スクール襲撃事件についての記述は、学生時代沢山読んだ、遠藤周作氏の小説を思いだした。 2016/12/14