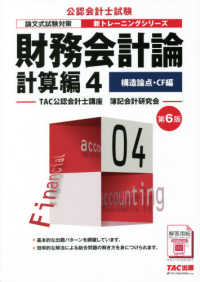著者等紹介
チェーホフ,アントン・P.[チェーホフ,アントンP.][Чехов,А.П.]
1860‐1904。庶民の子として生まれ、中学の頃から苦学を重ねた。モスクワ大学医学部在学中も家計を助けるため、ユーモラスな短篇を多数の雑誌に発表。社会的関心も高く、結核を患いつつ社会活動や多彩な創作を展開した
ザトゥロフスカヤ,イリーナ[ザトゥロフスカヤ,イリーナ]
1954年モスクワの画家の家庭に生まれる。幼少時から詩を創り絵を描くが、絵画とグラフィックを正式に学び、最初の個展は1989年のロンドン、以後世界各地で開催。2002年モスクワ美術家同盟よりディプロムを授与される。フレスコ、絵画、陶器、書籍デザイン、詩作、刺繍等広範囲に活躍。作品は12カ国の美術館に収蔵され、個人コレクションも多い
中村喜和[ナカムラヨシカズ]
一橋大学でロシア語を学ぶ。日本貿易振興会勤務の後、東京大学、一橋大学、共立女子大学で、ロシア語を教える。専攻はロシア文化史。日露関係史にも関心をもち、論考を発表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ケイ
39
「すぐり」「恋について」との三部作の一作目。獣医と中学校の教師が、猟で遅くなり村長の家に泊まった晩、教師が獣医に語った話。杓子定規で、規則を遵守できているかいつもう憂慮している同僚のベリコフ。彼のせいで生活が堅苦しくなると村人皆が彼を疎ましく思い、新しく村に来た女性と結婚させることで懐柔しようとする。彼はショックから死亡するが、彼はまさに棺桶がぴったりのような性格だと誰もかなしまない。しかし、彼がいなくとも生活は堅苦しく遵守しなければならない規則に村人は後から気づくのだ。チェーホフの皮肉めいた作品。2014/01/27
にゃおんある
23
主人公は、晴の日でもオーバーシューズと傘を常に持ち歩く極度に型に嵌った教師。何でもかんでもケースに入れるでしょ。周りから疎まれ揶揄されて挙句には醜態を晒したことを気に病んで死んでしまう。その日は雨でみな厄介者が居なくなったことにほくそ笑みながらオーバーシューズと傘を差しながら弔うのです。自由。それを感じるのも束の間、奇妙なことにみなが箱という呪縛に囚われていることに気付く。周りにはどうでもいいことの束縛が山とある。彼がニヒルだったように彼に対してニヒルに、そして社会全体が冷笑を浮かべている。2018/01/30
gogo
13
ずっと箱に入っていたい男をめぐる物語。彼は今でいうコミュ障であり、村で苦労を重ねる。周囲にすすめられ、女性と交際するのだが、性格が禍いして彼女の弟と喧嘩し、家に引きこもり、死んでしまう。男の死後、村の人々は開放感に浸る。しかし、暫くすると村は以前と同じ重苦しい空気に覆われてしまう。実は、村人たち自身も、それぞれの箱に入っていたことに気がつく、というオチ。チェーホフが短い物語で活写した、ムラ社会の閉塞感とは、どの社会でも似たようなものなのかもしれない。2016/06/06
いしりば
3
型にはまった男の悲喜劇いつもあらゆる不安を抱えながら規則正しくする男によって村全体が規則に従わなければならない息苦しい箱のようなものになってしまったというのは「眼差し」による支配の規律訓練のようあと、おそらく官僚主義とか労働の疎外みたいなものも書かれてるのかな2014/04/13
ちあき
3
『すぐり』と同じくイワン・イワーヌイチとブールキンが登場する作品。人物造型の手法は「誇張によるカリカチュアライズ」なのだが、描き出されるキャラクターには、姿かたちを変えてこの国この時代で生きつづけているかのような存在感が宿っている。これが普遍性ってやつなんだろう。読後感は重く、しかもボディブローのようにきいてくる。2009/01/09
-
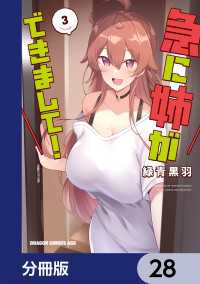
- 電子書籍
- 急に姉ができまして!【分冊版】 28 …
-

- 電子書籍
- 氷の城壁【タテヨミ】 76 マーガレッ…