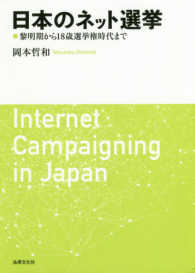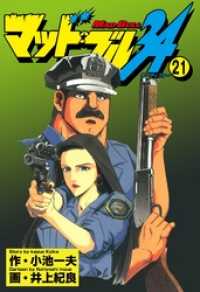内容説明
幻想は絶えず自身を養い続けそれ自体の織り出す夢により疲れを知らずに増殖する―ラマ教遺跡の噂に中央アジアのシルクロードを訪れた考古学者が一人、突然襲う砂嵐の中、13世紀と思われるオアシス都市にワープする…幼い頃の思い出を魂の片隅に留める者には、星辰と共に言いようもなく懐かしい夢物語。
著者等紹介
ブリヨン,マルセル[ブリヨン,マルセル][Brion,Marcel]
1895~1984。アイルランド系の父と南仏に先祖を持つ母の間にマルセイユで生れ、ラテン的知性とゲルマン的感性の対話の中に育つ。その広範な知識から美術評論家、考古学者、伝記作家、歴史家、小説家と多様な場面で活躍し、1964年アカデミー・フランセーズに入会
村上光彦[ムラカミミツヒコ]
1929年、佐世保に生まれる。1953年、東京大学文学部仏文学科卒業。成蹊大学名誉教授、大佛次郎研究会会長、鎌倉ペンクラブ副会長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mii22.
52
言葉の贅沢を味わい幻想的な文章に酔わされる至福の時。本を読む幸せな気持ちで満たされる。シルクロードを訪れた考古学者が突然砂嵐に襲われワープしたのは13世紀と思われるあるオアシス都市。そこでなんとも魅力的な人々に出会い、長い人生をその地で過ごす...。もうずっと読んでいたい、現実に戻りたくない、そんな気持ちにさせられる。素敵。2016/03/06
syaori
28
大変好みです。砂から生まれ砂に返っていく砂漠の蜃気楼のような本です。「砂の都」に行き着いた主人公の街での生活を描く物語は終始静かな語り口で語られ、大きなうねりもなく、割合淡々と進むのですが、とにかく楽園のような「砂の都」が魅力的です。大きなバザール、金銀細工師が差し出す瑪瑙の指輪、次々と広げられる絨毯、講釈師の語る物語などが、後半、忍び寄ってくる死や滅びの気配とともに印象深く残ります。夜に開く花のような、静かで豊かな香りをたたえた世界で、本を閉じた後も失われた街が郷愁とともに思い出されてなりません。2016/04/13
rinakko
18
大好きなので再読。素晴らしい。その幻想美に魅了されて目を瞠るようだった情景の数々が、終にはまた砂へと還ってしまう…。そんな物語なのに(だから)、ただ静かに慰撫される。ひろい愛と宇宙との繋がりを説く、少し風変わりに思える独特な教義に基づいて生きる〈星々の息子たち〉と、都に住みついた主人公との深い交流がしみじみとよかった。物語を貫く豊かな思惟、自由で揺るぎない人々の清廉な姿。こんな風に生きられるものならね…と、共感と憧れで胸が満たされる。“品物”自体の持つ気品や美しさは全て貴重である…という考え方がとても好き2015/06/30
いやしの本棚
15
リチャード・ダッドの青い砂漠の絵が浮かんでくるような導入部。砂嵐に巻き込まれ、目覚めるとそこは、かつて砂に呑み込まれた13世紀のオアシス都市…。でも主人公は、そういうことははっきりと自覚せず、新しい自分と出会えるという意識のもと、いつのまにか砂の中の都市になじんでいくので、SFやタイムスリップものというより、観念的な幻想小説という印象。砂漠や隊商の旅になぜか惹かれてしまう人にとっては、魅惑的な物語と思う。随所で砂漠を舞台にしたダンセイニの幻想短篇を思い出した。砂に消えていく都、遠ざかる隊商の影…2016/07/17
kthyk
14
大草原と砂漠が広がる乾いた海。見捨てられた都市の上を、かってそこが肥沃で豊かな大地であったことも知らず、隊商を組んで、無定型な平地を渡って行く物語。この物語は異次元の時間がテーマ。前作「城」は森の中の相補性的「空間」、そして今回の「都」は砂の上の相対論的「時間」。因果論では描けない時間を彼はSF的手法で書く。時間の始まりから終わりまでの旅をブライアン・グリーンは「宇宙の歴史上、秩序と無秩序とのあいだでつねに繰り広げられてきたエントロピック・ツーステップ」と言った。それは世代の上に次の世代が生む入れ子物語。2023/12/06