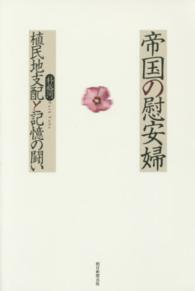内容説明
東南アジアに近代国家が導入される以前から、現在のマレーシア、フィリピン、インドネシアにまたがる海域を自前の生活圏として暮らしてきた海サマ。典型的な国境をまたぐ社会であった海サマ社会は、マレーシア国家に組み込まれたあと、その制度や政策とのかかわりでいかに変容してきたのか。国境は海サマにとってどのような意味を持つのか。サバ州センポルナの海上集落で幾重にもフィールドワークをかさね、開発と宗教の領域における変化を手がかりに、かれらの国家経験を探る。
目次
序 海サマと国家・国境という課題
フィールドワーク―国境社会をいかに捉えるか
1 民族の生成と再編(海サマとはどのような人びとなのか―国境をまたぐ民族の概要と先行研究;スル海域とサバ州の歴史過程―民族の生成を中心に ほか)
2 開発過程と社会の再編(地域社会の分断と政治的権威の再編成―国境の町センポルナ;海上集落の構成と歴史―調査地カッロン村の概況 ほか)
3 イスラーム化と宗教実践の変容(サバ州におけるイスラームの制度化と権威―法・行政・教育;「正しい」宗教をめぐるポリティクス―海サマのイスラーム化と国家 ほか)
結び 国境社会を生きること
著者等紹介
長津一史[ナガツカズフミ]
東洋大学社会学部・准教授。1968年札幌生まれ。1992年上智大学外国語学部卒業。1998年京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程単位取得満期退学。2005年京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科より博士(地域研究)を取得。日本学術振興会特別研究員PD(1998年から)、京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科助手(2000年から)を経て、2006年から現職。東南アジア海域世界の社会史、海民社会の地域間比較を研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。