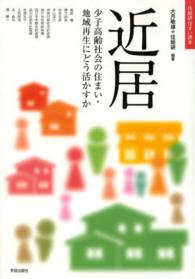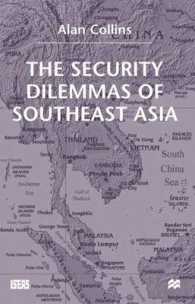内容説明
何が実験を成立させるのか?帰納的推論の復権をとなえ、欧米で科学研究費の審査方法にまで影響を与えたポストゲノム時代のバイオ研究論、待望の完訳。
目次
実験プログラムを定義する
科学プロジェクトのフレームワークとしての仮説―批判的合理主義は絶対か
仮説が実際的ではない科学研究の例
問題や問いを科学プロジェクトのフレームワークとして使う―帰納的推論への招待
問いに対する答えが得られたとき、それが受け入れられるものであると判断するためには何が必要か
実験結果をもとにして現実をどのように表現するか―モデルの構築
実験系を確立する
実験をデザインする―用語の定義、タイムコース、実験の繰り返し
モデルの有効性を確かめる―未来を予測する能力
実験プロジェクトをデザインする―実際の生物学の例〔ほか〕
著者等紹介
白石英秋[シライシヒデアキ]
1960年前橋市生まれ。1983年京都大学理学部卒業。京都大学大学院理学研究科生物物理学専攻を修了後、岡崎国立共同研究機構基礎生物学研究所助手、京都大学理学部化学教室助手、同講師などを経て、京都大学大学院生命科学研究科准教授。理学博士。研究分野は、RNAの分子生物学と微細藻の分子生物学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ehirano1
66
約10年ぶりに再読しました。ガチガチの専門書なのですが、10年前に線を引いたところに懐かしさを感じながら、時には苦笑いしながらのノスタルジックな読書になりました。しかしこの本よくできてるな~。2020/09/12
彦坂暁/Hikosaka Akira
1
生命科学における実験デザインについての本。科学哲学・認識論をベースにして原理的なところから説いているのが面白い。著者はポパーなどの批判的合理主義にはっきり反対する立場をとり、帰納的方法の意義を強調する。その上で「仮説」ではなく「問い」を研究プロジェクトのフレームワークとして使うこと、帰納空間へのアクセス、実験における対照(コントロール)の設定方法、モデルを構築する意義、モデルが未来を正しく予測できるか確認することの必要性、など、研究を進めて行く上で肝になるところを、分かりやすい例を挙げながら丁寧に解説して2012/02/16
-
- 洋書
- Femlandia