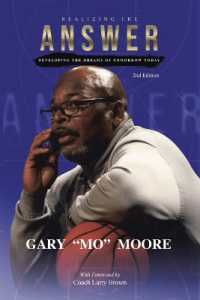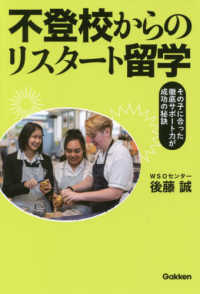内容説明
社会学や社会心理学のフィールドワークでは、研究者と調査の相手とのかかわりが、常に問題となる。本書はその両者のかかわりを捉えなおすテクストであり、生活史の社会調査をするさいの方法的態度が示されている。本書では、ゴフマン、ギアツ等の豊富な事例やフィールドワークを、批判的に吟味することによって、解釈的相互作用論の視点と態度が具体的に追体験できるようになっている。
目次
第1章 解釈的視点
第2章 個人誌的経験の確保
第3章 解釈過程
第4章 解釈を状況づけること
第5章 濃い記述
第6章 解釈の実行
第7章 結論―解釈的相互作用論
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひつまぶし
2
エピファニーとは「キリスト教的神の現れや印」と本文中にはある。おそらく「気づき」くらいの意味で、質的研究において感覚的理解を重視したいがために、エピファニーなどと大げさな言葉を採用して重みを持たせたかったのだろう。昔から質的調査の方法論にまつわる本は読み通すのが大変なわりに何の役にも立たないと思わされてきた。センス・オブ・ワンダーの扉の見つけ方や見つけた扉の開け方が知りたいのに、扉を開けた後の処理方法ばかりくどくどと書いてある。しかし、30年前の訳書だと思えば、今なお道のりは遠いものの、発展はあるのかな。2021/08/28