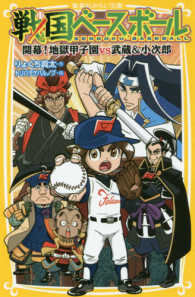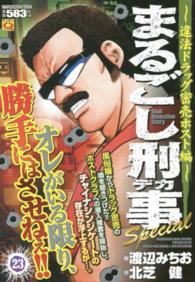内容説明
本を編む、場を編む、人を編む…出版の可能性を探りつづける9人へのインタビュー。
目次
第1部 個人の表現としての“本”(情熱と持続―小西昌幸;自分出版という選択―竹熊健太郎;コピー本魂―堀内恭)
第2部 “本”が場をつくる(情報誌という運動体―村元武;スクラップ&ビルドの街でつながりを生み出す―大竹昭子;“街とメディアと市民”のかたちを模索して―本間健彦)
第3部 “本”から地域を見つめる(画家と出版―牧野伊三夫;雑誌で地域を再発見する―小林弘樹;町とともに忙しく楽しく―山崎範子)
著者等紹介
南陀楼綾繁[ナンダロウアヤシゲ]
1967年、島根県出雲市生まれ。ライター・編集者。早稲田大学第一文学部卒業。明治大学大学院修士課程修了。出版、古本、ミニコミ、図書館など、本に関することならなんでも追いかける。2005年から谷中・根津・千駄木で活動している「不忍ブックストリート」の代表。各地で開催される多くのブックイベントにも関わる。「一箱本送り隊」呼びかけ人として、石巻市で本のコミュニティ・スペース「石巻まちの本棚」の運営にも携わる。本と町と人をつなぐ雑誌『ヒトハコ』(書肆ヒトハコ)編集発行人(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kokada_jnet
20
ミニメディア編集者の方たちへのインタビュー集。自分的には『谷根千』の山崎範子さん分がよかった。2019/01/31
阿部義彦
17
2017年11月末発行、版元は「雲遊天下」を発行しているビレッジプレスです。著者は「一箱古本市」の発起人でもあります。去年新刊の時は店頭で何気なく買い損ねてたんですが、最近南陀楼綾繁さんの著作をよく読む様になって、そこからミニコミ誌(プレイガイドジャーナル 、ハードスタッフ、コミック・マヴォetc)タウン誌等に取り憑かれた割と表に出ることの少なかった編集者達にインタビューを試みて貴重な証言を引き出しています。ガリ版でのホッチキス留め、またはコピーを綴じただけの冊子からの出発!自分が読みたい本を作るが原点。2018/04/08
チェアー
11
さまざまな立場で本や雑誌を作り続ける人。訴えたいこと、自分の好きなことを、紙の物体を通じて世に問うひとびと。この本に採り上げられている人達は、「大変だよ」「苦しいよ」と言いながら、とても楽しそうだ。これからミニプレスなどを手に取るときは、その向こうに、楽しそうに「しんどいよ」と笑う人の顔を思い浮かべると思う。2018/01/26
さすらいのアリクイ
8
編集者、南陀楼さんが雑誌を作っていた方たち、雑誌を作っている方たちへのインタビューが載っている本。新宿プレイマップ、プレイガイドジャーナルなどかつて雑誌を作っていた方、新潟の雑誌ライフマグなど今雑誌を作っている方にも雑誌を作るときに何をしている(していた)のかとか、雑誌へのこだわり、今後どうしたいのかなどを南陀楼さんが聴いています。インタビューを読むことでかつてあった雑誌の話から雑誌があった頃、時代の空気が頭のなかに浮かんだり、今ある雑誌では題材にしている地域のことが理解できたりなど。いい本だと思います。2018/09/16
qoop
5
同人誌、ミニコミ、タウン誌といった作り手と読み手の距離が近い本。そうした本を通じて人と人とのつながりが生まれると著者は説く。趣味や価値観、生活情報を共有することで読み手が作り手になり、出版の輪が広がり深まる。その可能性を著者が聴き取ったのが本書。本というのは止むに止まれぬ気持ちの表明だったり、あふれてしまった某かの受け皿だったりするのだなと感じた。文章や絵画が創作の一次産業(変な言い方だが)だとしたら本というのは二次産業だと思っていたけれど、違うのかもしれない。どちらも差異なく一次産業なのかも。2019/10/24