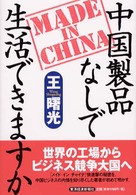目次
はじめに―「読めない名前」はなぜ増えるのか
1 「世界に一つだけの花」としての子どもたち
2 読めない名前と失われた「公共空間」
3 「個性的な名前」ブームの起源
4 親密空間における「子どもという価値」
5 情報=消費社会における「たまひよ」名づけ本
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Riju
2
現時点でこの手の文献では新しめのもの。ページ数も少なく文献っていうよりは講義などで渡されるハンドアウト的な印象。それでも押さえるところは押さえているし、内容についても納得できるところが多かったかと。もっと根拠となる実験、調査があれば、尚更良かった。2014/11/21
hixxxxki
1
個性的な名前は2000年頃から増えてきた。従来は漢字や意味から名前を決めていたが、音から名前を決め、漢字を当てはめるという決め方が増え、加えて、個性化を求める結果、読みにくい漢字が選ばれてしまうことで、個性的な名前が増えている。たまひよやネットのデータベースも関係している。出産が社会的な義務から、母親の個人的な選択の結果と考えられ、私的な行為となったため、子の名前も読んだ時の心地よさが重視される。親密空間の重視と、公共空間が単なる消費空間となったことにより、名前の持つ公共性に対する考え方も変わってきた。2015/09/21



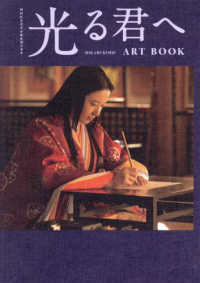
![合格対策データサイエンティスト検定[リテラシーレベル]教科書](../images/goods/ar2/web/imgdata2/48659/4865943412.jpg)