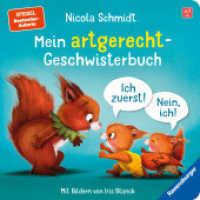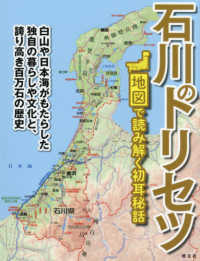目次
第1部 子ども・学生の貧困の実態と学ぶ権利の保障のためのとりくみ―教育現場からの報告(「いま」を生きる高校生に共感と希望を―全日制高校の現場から;「無力でも微力でもない」高校生は社会を動かす―「大阪の高校生に笑顔をくださいの会」のとりくみ;定時制高校の実態と高校生・教師のとりくみ;学費値上げストップから学費負担軽減へ―流れを変えた学生のとりくみ;東京・足立区における子ども・親の生活実態と教育;「子どもの貧困」から「学力の保障」へ;貧困に負けない、生きる力をつける)
第2部 学ぶ権利の保障のために―その問題点と課題(就学援助制度の市町村格差問題と課題;学校は貧困にどう立ち向かうか)
著者等紹介
宮下与兵衛[ミヤシタヨヘエ]
長野県・定時制高校教諭、東京大学大学院博士後期課程(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう。
23
2010年初版。新自由主義的構造改革が進む中で、学校現場で貧困がどのようにあらわれてきているのか、そのなかで学ぶ権利を保障するためにどのような取り組みが行われているのか、そのための課題と問題点は何かを考察した内容となっています。全体的に現場からの実践報告が多く、「貧困の『底抜け』と同時に、学力と意欲の底抜け」も生じているという指摘は大変重大だと思いました。また、貧困が拡がっているからこそ、教育と福祉とが連携していくことの重要性が指摘されていました。2016/11/30
katoyann
19
2010年刊。高校教諭が中心となり、高校生の貧困の実態と学習権保障の課題について考察した本。就学援助率は本書の中で13.9%とされているが、就学援助は自治体裁量であり、財政規模の小さい自治体の場合はニーズのある子どもに援助が届かない場合もある。公立校でも授業料を除いた教育費は年間40万円以上かかると言われているが、年収200万以下の世帯も増えている中で、学習権が貧困により侵害されているケースも目立つ。例えば、アルバイトで教育費を稼ぐ子どもの増加である。教育費の完全無償化が政策の鍵となるだろう。2023/05/21