目次
第1章 英語教育の現状と課題
第2章 日中の英文法教育に関する先行研究
第3章 英語科教員による実践
第4章 国語科教員による実践
第5章 メタ文法プロジェクトの実践と授業デザインのポイント
第6章 メタ文法能力の育成を目指した英語授業の分析
第7章 メタ文法能力の育成に向けた授業案
第8章 メタ言語能力の育成を基盤に置いた言語教育を目指して
第9章 コンピテンシーの育成を核とする教育イノーベーションへの挑戦の試み
著者等紹介
秋田喜代美[アキタキヨミ]
東京大学大学院教育学研究科教授、同研究科長・教育学部長
斎藤兆史[サイトウヨシフミ]
東京大学大学院教育学研究科教授
藤江康彦[フジエヤスヒコ]
東京大学大学院教育学研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Nobu A
4
一知半解だから流し読み読了なのか、流し読み読了だから一知半解なのか、正直分からない。言語を高次から観察・分析するメタ言語能力を文法に特化したのが「メタ文法能力」。タイトルに英語科と国語科の連携とあるが、具体的にどんな連携だったのか不明。今まで密接な連携がなかったと言う前提だろうが、何故そうだったのか、その結果、言語習得がどうだったのか等、現状把握が明確に出来ずに、検証が厄介で掴み所がないメタ文法能力を扱っているような。趣向を凝らした色んな授業は素晴らしいが、研究手法枠組みが非常に難しい印象を受ける。 2021/03/23
ダヴィ
0
★9 流し読み。教科横断的が叫ばれている中、この本にあるメタ言語(文法)能力の育成は非常に重要になってくると思われる。英語と国語の連携の歴史についても非常に詳細に記述されており、装丁も含めて好きな本である。 ただ、「連携」の授業での学習内容が非常に難しく、進学校以外では現実味のないものに見えてしまう点と、本書の記述がやや英語科に偏っており国語科側からすれば物足りない点が課題か。 いわゆる教育困難校や公立中での授業例をもっと見てみたい。2024/03/15
-

- 電子書籍
- 愛だけ知らない 分冊版 10 マーガレ…
-
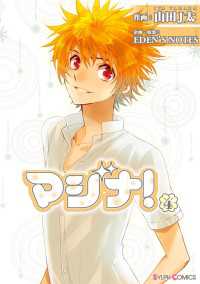
- 電子書籍
- マジナ!(4) シルフコミックス







